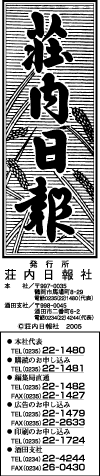- 音声ブラウザをご利用のお客様向けのリンクです。
- 本文へジャンプする
荘内日報ニュース
2011年(平成23年) 12月4日(日)付紙面より
ツイート食べ物を大切に 鶴岡地域学校給食 明治時代の献立再現
旧鶴岡市内の小中学校で2日、明治時代の献立を再現した「おにぎり給食」が行われた。子供たちは塩味だけの素朴なおにぎりを味わい、食べ物の大切さを学んだ。
日本で最初の学校給食は1889(明治22)年に当時の鶴岡町の大督寺境内にあった私立忠愛小学校で、家庭の生活が苦しい子供たちに昼食を支給したのが始まりとされる。
おにぎり給食は、「学校給食発祥の地」を記念し、鶴岡市学校給食センターが、給食100周年を迎えた1989年から毎年12月に実施している。給食が始まった当時の献立が再現され、学校側からも「教育的にも意義深い」との声があり、以来、給食記念日の“定番”となっている。
この日は旧市内14校で実施。メニューは具が入っていない塩味だけのおにぎり1個と焼いた塩引き、イタドリのいり煮、牛乳の4品。中学校にはナメコ汁が付いた。
朝暘第四小学校(矢口研一校長、児童517人)の1年3組では、「いただきます」のあいさつで給食が始まると、児童たちはおにぎりを両手に持ち、口を大きく開けてかぶりついていた。児童たちは「とてもおいしい。毎日、この給食がいい」といつもと違う給食に大喜びしながら味わっていた。他の13校は今月9日に実施される。
2011年(平成23年) 12月4日(日)付紙面より
ツイートキビソ 多彩な魅力発信 松ケ岡で製品展示
蚕が繭を作るときに最初に吐き出す糸・キビソを使った絹織物製品の「鶴岡きびそ展」が、鶴岡市羽黒町松ケ岡のギャラリーまつで開かれ、さまざまな風合いの衣類やバッグなどが、訪れた人にシルクの新たな魅力を伝えている。
「鶴岡シルク」のブランド化戦略を進める鶴岡織物工業協同組合(鈴木重雄理事長)が、鶴岡の絹織物産業の原点である松ケ岡で初めて開いた。会場がある旧蚕室の1階には昨年6月から、キビソ製品のアンテナショップを開いているが、規模を拡大した展示であらためて魅力を発信する狙い。
展示したのは、キビソのごわごわした質感を生かしたタペストリーをはじめ、荒く紡いだ糸で木綿のようなザックリとした風合いを持つクッション、キビソの真綿を紡いだ糸で柔らかい手触りのタオル、ストール、スリッパなど約30品目の約100点。
このうち新作のトートバッグは、キビソを織り込んだ帆布地を使ったもので、しっかりした造りながら柔らかさとぬくもりを併せ持つなど、いずれもシルク特有の奥深い風合いと落ち着いたナチュラルカラー、洗練されたデザインが特徴だ。
訪れた人たちは、それぞれの手触りを確かめ、キビソの多彩な顔を楽しむように見入っていた。
展示は4日まで、時間は午前10時―午後4時。特別協賛セールとして組合加盟各社がスカーフやネクタイなどのシルク製品、キビソの原糸、シルク生地などを特別価格で販売している。また、アンテナショップでは期間中、全品を1割引きで販売している。