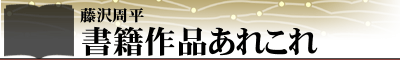- 音声ブラウザをご利用のお客様向けのリンクです。
- 本文へジャンプする
「鎮守の森(1)」 からのつづき

『春秋山伏記』には、今ではすっかり喪(うしな)われてしまった感のある村の共同体の姿を描いていて、郷愁をそそられる。村の鎮守の神さまも村の人たちの生活に溶け込み、喜怒哀楽を見守っていたようだが、今もそうなのだろうか。祭りの賑わいをとり戻すためいろいろな試みはされるようだが、難しいようだ。
『蝉しぐれ』にも祭りが登場する。こちらは、海坂藩の城下の熊野神社の祭りで、夏の祭礼である。派手な鉾山車(ほこだし)と踊りで城内外の人々を魅了した。山車は各町内から15台も出て、踊り手は男女300人も出るという、盛大な祭りであった。しかも夜祭りで、無礼講となったこの夜ばかりは仕事や身分の上下を忘れて騒いでもよいのである。文四郎は隣家の娘のおふくを連れて祭りを見物に行った。少年のころの大切な想い出として、文四郎の心に一生刻み込まれる一夜であった。おふくとはその後別れる運命が待っている。そのことも知らず祭りを楽しみにする二人の姿がいじらしい。
藤沢さんの作品に祭りはあまり多く出てこない。子供のころの天神祭の思い出や村の薬師神社の祭りの思い出を、今となってはお聞きすることもかなわないが、このような作品を通して、作者の祭りに寄せる懐旧の情を読み取ることができる。
(筆者・松田静子/鶴岡藤沢周平文学愛好会顧問)
Loading news. please wait...