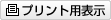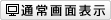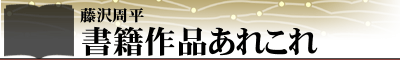- 音声ブラウザをご利用のお客様向けのリンクです。
- 本文へジャンプする

◇深川の春
今年の春、私は東京の江東区深川の辺りを訪ねてきた。ある1枚の写真が頭の中にあって、その同じ場所に行ってみたいというのが一番の目的だった。その写真というのは、藤沢周平さんが、「深川江戸資料館」にある模擬長屋の一角で、帳場格子に座している写真である。それは「深川江戸散歩」(新潮社)という本に載っていたもので、深川周辺の今昔に触れた藤沢周平さんの文章に添えられたものの1枚であった。つき米屋の帳場には大福帳や大きな算盤(そろばん)などがあり、江戸時代の小さな商家の雰囲気を再現している。深川は、藤沢周平さんの「市井もの」といわれる作品の主な舞台である。そこは、職人、通い人、商人、ぼて振りと呼ばれるかつぎ商人、日雇い、料理屋づとめの女、果ては娼婦までさまざまな町人が暮らす町、辰巳芸者と呼ばれた深川芸者もおり、門前仲町は遊興の場として夜な夜な賑わった町である。その町に生きる名もない庶民の暮らしを描き、生きる辛さと歓びを描いた作品は多くの読者を魅了している。私の好きな作品もその「市井もの」である。こうした小説の舞台である深川を、初めて訪ねたのである。
江東区の南砂という町に住む私の教え子のSさんは、共同通信社の記者をしていて、藤沢さんの愛読者でもある。Sさんに道案内をしてもらうことにして、両国駅で待ち合わせた。両国から深川門前仲町まで歩きながらの探訪は結構な距離でくたくたに疲れたが、楽しい1日であった。「小名木川」の河口、つまり隅田川に合流するあたりに架けられた「万年橋」の近くには、芭蕉記念館もあり、芭蕉が借りて住んでいた芭蕉庵の跡もある。小名木川を遡ってゆくと「高橋」という橋がある。この2つの橋は、作品の中に頻繁に登場する橋で、見たことのない私にも、その橋の上からみえる川面の光のきらめきや、橋の下をゆく舟のたたずまいを想像できるくらいであった。こうした深川の町を何故藤沢さんは好んで描いたのだろう。そのことも考えたかった。
春の陽光は眩しく、少し汗ばむほどの温かさで、桜も五分咲きというころだったので、隅田川の川べりの遊歩道に咲き乱れるさまざまの花も美しく、今年の1月に藤沢さんが亡くなられたことの悲しみを、ひととき忘れるくらいだった。深川江戸資料館で例のつき米屋の帳場に私も座り、算盤にさわったりした。この長屋を模した空間はとても面白く、ミステリアスに作られている。1日の時間の流れや1年の四季の流れを音響や照明の効果で雰囲気を作り、例えば朝の蜆(しじみ)売りの声が入ったり、夜、雷雨があったり、猫の鳴き声がしたり、とても演出に凝っていて、江戸時代の人間になったような気分が生まれてくる空間だった。
◇文学の土壌
藤沢周平さんの生まれた村、黄金村の高坂字楯ノ下(現・鶴岡市高坂)は、金峯山の麓にある。その楯ノ下をぐるっと巡るように青龍寺川が流れていて、その川を中心に水路が村中を走っている。本名、小菅留治少年は、感受性の鋭い、利発な子供であったに相違ない。「青龍寺尋常高等小学校」に入学した留治少年の写真は、どれもキリリと口を結び、目元にはにかみを残しながら写っている。少年は5年生のころ、吃音(きつおん)症になってしまったとエッセイに書いてある。感受性の鋭い少年は、自己表現がうまくできなかったり、神経が圧迫されたりしたときに、よくこうした症状をみせることがある。留治少年の神経を圧迫したものは何だったのか。それはエッセイに書かれたものからしか想像できないのだが、私はこのころ留治少年の心に既に「文字」の下地となるものが宿ったのではないかと思う。心に思うことがうまく口に出して言えず自然と内向的な少年となってゆくが、物静かな少年はその目で見たもの、聞いたことを深く心の裡に沈殿させていったに違いない。
例えば、少年が小学校に夕方まで残ったことがあって、帰り路、何気なく振り返ったときに、既に日の沈みかけた金峯山の麓の小学校が、巨大な影に覆いつつまれているのを見たシーンをエッセイに描いている。(『ふるさとへ廻る六部は』村の学校)この風景は感受性の鋭い少年の心に何を刻んだのだろうか。少年は、そのとき校舎の中からうつくしく澄んだ合唱の声を聞き、また、東を振り向いてまだ光のあたる稲田を見、「牧歌的な」光景だった、と藤沢さんは回想しているが、私にはこの少年の心にはもうひとつのもの、つまり「闇」が映ったような気がしてならない。目の前に迫る闇と、むこうの光、この対照が少年の見たひとつの原風景であって、やがて作品のトーンとして甦ってくるのはあるまいか。
金峯山は夕陽の沈む山というイメージがある。鶴岡市内に住んでいる今は金峯山は南の方にみえるが、私の生家は鶴岡市黒川(櫛引地区)にあるため、朝日は月山から昇り、夕日は金峯に沈むのを毎日見て育った。金峯や西山が既に黒々と闇に包まれているのに、月山はなお残照でキラキラ輝いている風景に神秘的な何かを感じて育った。特に晩秋のころ、月山に雪が降って、山の頂きが赤く輝いているような姿は忘れ難い。だから、その金峯山の麓に抱かれた青龍寺の村やその小学校が他よりも早く闇に包まれるのがよくわかる。少年が見た「闇」と残照の「輝き」はとても鮮烈だったにちがいない。
◇旅人のこころ
サイトのエッセイ集『ふるさとへ廻る六部は』には珍しく2編の詩が掲げられている。冒頭の「忘れもの」という詩と終わりの「冬の窓から」という詩である。どちらも故郷への思いをよみこんだものである。特に「忘れもの」の詩には作者の心の隅にある、いつも充たされることのなかった空虚、それは郷愁と言うべき感情かもしれないが、それだけでは片付かない、底知れぬ空虚感がよみとられる。「置き忘れたもの」をそのままにして「旅に出た」ことを悔やむ気持ち、「捜しに戻って」みると、そこには既に見知らぬところと化している、そのいらだちと哀しみ、自分ひとり旅に疲れ、帰るあてどを喪っている、という孤独感が、ストレートに表現されている。小説やエッセイには表現しなかった「感情」が裸のまま投げ出されている。終わりの「冬の窓から」という詩も同じである。「私の悔恨をつめこんで、凍いた腸詰のように光る故郷」という文面にも、故郷への思いがそのまま表現されている。いつも心は故郷へ向いていながら、故郷から外れてしまった自分、都会の雑踏の中で生きる道を探してきた自分、そんな半生をかえりみると、いつもあてどのない旅人の気持ちがどこか心の底にあることを見据えていたのだろう。
江戸時代、深川には諸国から集まってきて住みついた人が多かったという。なんらかの事情で故郷を離れ、客地である江戸に住みついた人々が貧しさや病苦に耐えながらも精一杯生きていた町であった。藤沢さんは時代小説を通して、人間の生きる哀しみと歓びを描いた。深川を描いたのも、そこに生きる人々の闇と光に引きつけられたからであろう。どの人も心に闇を抱き、充たされない空虚を抱き、ときどきは光も見ながら生き、そして死んでゆく。現代に生きる私たちも同じである。そんな人間の姿を描き、読む人の心をなぐさめてくれた藤沢さんは、もう遠い人となってしまった。今度の旅には、どの文庫本を道づれにしようか、と本棚をながめている私の心もまた充たされぬ思いが次第に大きくなってゆく昨今である。
藤沢周平さんのご冥福を心からお祈りする次第です。
(1998年1月28日発行「鶴翔同窓会だより」に掲載されたものを再掲したものです。)