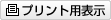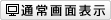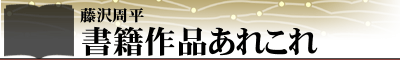- 音声ブラウザをご利用のお客様向けのリンクです。
- 本文へジャンプする
2 ふるさとの風景
◇風景の中に生きる人間
藤沢氏の小説では風景描写が重要な位置を占めている。例えば江戸を舞台とした小説であれば、「大川端」の朝霧の風景、真昼の町の家並みの上に浮かぶ雲の描写、屈託した心を抱く若者がふと見る路傍の花の色、風のそよぎに翻る葉裏のきらめき、遠くの山頂を染める夕日の一瞬の輝き、といった描写が読む人の心にくっきりとしたイメージで伝わり、しかも一種の懐かしさ、郷愁の情感を抱かせる。その風景を見ている登場人物の眼差しがそのまま読み手自身の眼差しであるかのように。ここから読者は「時代のぬくもり」を感じ取ることができる。これが時代小説を読む楽しみの1つであるのではないだろうか。
氏がこの風景描写を大切にしていることはエッセイなどに述べている。例えば、
私は小説に風景を書くことが多い。そこに足をすえないと物語を進められないということがありますね。
やっぱり育った土地というものは人間形成に抜き差しならない影響を残すものでそのせいじゃないかと思います。
私が生まれた山形県鶴岡市の郊外の村 (旧・東田川郡黄金村大字高坂)は、東に月山が、北には鳥海山がそびえ、その前面に庄内平野の田んぼや畑が広がっていました。
また村のうしろは低い丘で、すぐそばを幅四、五間の川が流れているという、典型的な農村でした。村はずれの橋の上にあつまって日が沈むまで遊んでいると、やがてご飯を炊く煙が村の中にたなびく、そんな風景が、私の小学校五、六年生ころのものでした。
(藤沢周平きき書き『とっておき十話』「少年の頃の原風景」)
と、郷里での少年時代にみた風景を語っている。また、
特別の事情がないかぎり、郷里をはなれて暮らす者にとっては、自分の生まれた故郷ほど懐かしい場所はないだろうと思う。
私なども、東京に住んでもう三十年にもなり、その三十年という年月は郷里で暮らした年月より長くなったのに、いまだに東京暮らしは仮の生活であるような感覚が抜け切れず、折りにふれては郷里の四季の移り変わりを思いうかべ、喰べ物の味を思いうかべる癖がとれないのである。
実際にはわが郷里山形県荘内地方は、冬は雪がつもり、海から来る強い北西風が吹き荒れる土地である。
いまになって帰り住むには、その冬のことを考えるといささかためらわれる土地だし、食べ物にしてもむかしのままの味ではないということも聞く。すると私が郷里を思い懐かしむ気持の中には多分にただいまの現実と食い違う思いこみの部分やら、錯覚の部分やらが含まれているに違いないのだが、その思いこみゆえに、郷里はいっそう懐かしく、わが永遠の望郷の土地に思われて来ることも否みがたいのである。
(藤沢周平エッセイ集『小説の周辺』「緑の大地」)
と、故郷の風景とそこで過ごした少年の日々への郷愁を語っている。風景というものは、単なる眺望として人の目に焼きつくこともあろうが、多くは、その風景と共にあった自分や自分をとりまく人々への思いがあって初めて意味をもつものではないだろうか。故郷が懐かしいのは、そこに生き、生活し、山や川や草や木と触れ合った自分が懐かしいのであり、怖れ、喜び、悲しんだ自分のその時々刻々に見た一瞬の風景が焼きついていて何かの拍子に再現されるとき、人は誰でも郷愁をそそられる。ましてや田や畑を耕した思い出がある人にとっては土のぬくもり、風のにおいまで、自分の一部となっているであろう。逆にいえば、このような生の実感を持たない人にとっては、故郷の光景はどこの町、どこの村の光景であっても大した変わりばえのないものにあるのであろう。
こうした、誰の心にもある郷愁の念を満たされるのが、絵画や詩、小説などによってである。藤沢周平の作品にはこの出会いのチャンスがあり、そのことも楽しみの大きな要素である。