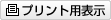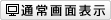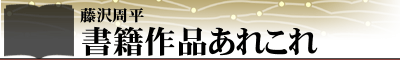- 音声ブラウザをご利用のお客様向けのリンクです。
- 本文へジャンプする
苦難の時代(下)
30歳くらいまで長い長い闘病生活を送るんですが、良くなったので就職活動をするんですけれども、鶴岡に帰る当ては全く無くなってしまって、日本食品経済社いわゆる業界新聞社に入ります。この4、5年は人並みの幸せをつかんだという一時期です。ところが36歳で長女が生まれ、その何カ月もたたないうちに奥さんが発病して亡くなるんですね。この時奥さんはたった28歳だったそうです。奥さんを死なせてしまったという悔恨というのはいろいろなところに出てきます。よく注意して読むと、「なぜ若い娘がこんな不幸せにならなければならないのか、若い娘はいつも笑っていなければだめだ」というような文章が出てきたり、この女を不幸にする男は最低だとか、そういう文章が出てきたり、慙愧の念と言いましょうか、悔恨の気持ちと言いましょうか、それらが作品に投影されている気がします。ちょっと気を付けてご覧になったらあちらこちらに見つかると思います。自分が病気になったとき以上にこの奥さんの死はこたえたようですね。非常に暗い気持ちになって、たぶん地獄を見たというような気持ちだったことでしょう。
この時国元からお母さんを呼び寄せて一番下の弟さんも東京にいれ、弟さんやお母さんに支えられながら子供を育てたようです。で、その鬱屈した気持ちをどう晴らしたらいいのか、そんな時自分が吐き出せるのは小説ではないか。ほかの家族に迷惑をかけること、例えばギャンブルに走るとか、ちょっと不良になるとか、そういうことをすれば家族に迷惑をかけるが、小説を書くことぐらいだったら鬱憤晴らしをしても家族には迷惑をかけないだろうと思ったそうです。書くことはある程度自分の気持ちを救うという面がありますね。最愛のものを無くした時、それを歌集にするとか句集にするとか或いは小説を書くとか。この間も和歌山のカレー事件で殺された子供のお母さんが童話を書いていましたよね。悲しみを昇華させる手段として、確かに書くということは効果があると思うんです。悲しみを悲しみとしてじっと耐えるのも大切だけれども、生き残った人は現実に生きていかなければなりませんから、悲しみを何らかの形で昇華させることは大切なことです。
藤沢さんが書くという手段によったということは、私達から言えば偉大な作家・藤沢周平の誕生なわけですから、よく書いてくれたというふうな気持ちになるわけですが、藤沢さんにとっては本当に辛さの捌け口として書かれたわけで、書いても楽しくなかったんじゃないかと思いますね。書記の作品は、題を見ていただくとわかりますように「暗い」「黒い」「闇」という言葉が多く用いられています。内容もあまり明るい展望はありません。ずっとそのような小説が続くんですね。
(山形県高等学校司書研修会講演より)