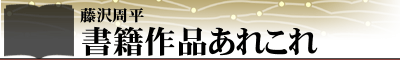- 音声ブラウザをご利用のお客様向けのリンクです。
- 本文へジャンプする
作品の魅力(下)
史伝ものの中では、私は、『一茶』が好きです。一茶は、「やれ打つな蠅が手を摺る足をする」「雀の子そこのけそこのけお馬が通る」とか「是がまあつひの栖か雪五尺」といった俳句から見ると人の良さそうなおじいさんのようですね。ところが一茶という人の実際の人生は、それはもうひどいもんです。人を騙したり争ったり、奥さんは4人か5人だか替えたりですね。俳句のイメージと実際の一茶は全く違うんですよね。この一茶が何故そのような人間になったかということや心理描写を面白く書いたのが、『一茶』という小説です。これは何というか、作家というものの心の地獄みたいなものを読み取ることができて面白い作品です。一時期藤沢さんもこの様な気持ちになったのかと想像しながら読むこともできますし、東京にいいて物書きになろうと思って、一茶もそうなんですけど、俳句師として成功しようと思ったけれど結局は田舎から出てきて一旗上げることは出来ず、また信州の奥深い田舎へ帰っていくという人生に自分を重ねたのかもしれません。実に面白い心理描写があります。それから『密謀』という小説は、これは直江兼次と言う人を中心に書いているんですけれども、史伝といっても忍者が出てきて半分はフィクションです。影の集団が出てくるこの忍者の描写があまり面白かったので、それはフィクションの部分なんですけが、史伝ものというよりフィクションになってしまったというような小説です。この2冊は史伝ものの中でも小説風で読みやすいものであるのではないかと思います。
三つに分類した作品の共通点は、どちらかというと主人公はお金もない、権力もない、地位も名誉もないほんとに弱い立場の人を取り上げて、その人が平凡な日常を送っていたのが突然様々な事件に巻き込まれて波乱万丈の人生を送るという設定が多いですし、特に海坂藩ものはそのようなものが多いですね。
(山形県高等学校司書研修会講演より)