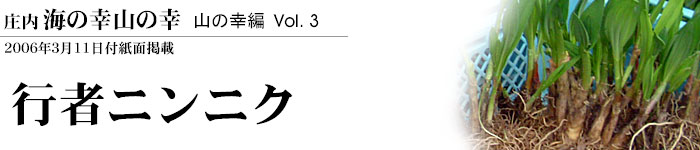- 音声ブラウザをご利用のお客様向けのリンクです。
- 本文へジャンプする
行者ニンニクは、その昔、山岳修験道の行者が荒行に耐える体力と精神力をつけるために食べたと言われる薬草だ。最近は、山菜、滋養強壮剤としても脚光を浴びている。庄内の農家が全国に先駆けて促成栽培に取り組み、中でも旧朝日村が先進地だ。タラノメ同様、転作作物として魅力的だった。
「うちの山には自生していなかったが、知人に種を譲ってもらい栽培を始めた。生のままでも、ゆでてもおいしい。強壮効果もある。それが魅力だね」。20年余りの栽培歴があり、鶴岡市朝日地区の産直あさひ・グーに出荷している佐藤多文さん=大網=は笑顔で話す。
行者ニンニクは、種をまいてから3年間育苗し、定植から収穫まではさらに4、5年を要する。商品として出荷できるまで最低でも7、8年かかる。長期的戦略を持った農家に栽培が限定される作物とも言える。生育に長い年月がかかるだけに自生のものが少なく、高値で取引されてきた。これまでは「庄内産」が全国をけん引してきたが、近年は自生の宝庫である北海道、秋田県でも栽培を始めた。後発のライバルたちがトップの座を脅かしている。
佐藤さんは転作田のほとんどを行者ニンニクの栽培に充てている。成長したものを秋にハウスへ移植し、3週間ほど加温。20cmほどに達したところで出荷する。全くの無農薬栽培。夏場は除草作業が待っている。手間暇がかかる山菜なのだ。

佐藤さんのハウスに入ると、ニンニクに似た香りが一面に漂う。根に近いところは白く、真ん中部分は赤紫色、葉は緑色でみずみずしい。「味はニンニクとニラの中間ぐらい。生でみそやマヨネーズを付けて食べてみて。ニンニク好きのひとには最高の酒の肴だよ。酒としょうゆの汁で浅漬けにしてもおいしい。ボリューム感を出すなら天ぷらだね」と話した後、「みじん切りにしてカツオのタタキの薬味にも使っているよ」と生産者ならではのぜいたくな食べ方を教えてくれた。
グーでは5~15本の50g入りを1パック400円ほどで販売している。生産者の中には行者ニンニクみそを売り出している人もいる。グーの女性スタッフは「風邪をひいた時に食べると体も温まるし、元気になるような気がする」と、「薬用効果」もPRする。
一番おいしい調理法として佐藤さんが挙げるのが炒め物。「肉やベーコンと一緒に炒める。味付けは塩こしょうだけで十分。肉を先に入れ、行者ニンニクは後。さっと火が通ったところで止める。しゃきしゃきしたのを食べてほしい」と話す。
グーでは4月中旬まで栽培物が並び、その後は自生に切り替わる。「こんなにうまい山菜はないよ」。8年の歳月がはぐくんだ「大地の味」に絶対の自信を持っている。
産直あさひ・グーのおすすめレシピ
行者ニンニクの卵焼き
○材料
行者ニンニク、卵、油、砂糖、しょうゆ
○作り方
- 行者ニンニクをよく洗い水切りし、できるだけ細かく刻む。
- 卵をボウルに入れ、油、砂糖、しょうゆを少量入れて溶く。
- フライパンに油を引いて「2」を流し込み、半焼きほどになったら、焼いた卵の片側に「1」を乗せ、もう片側を重ねて半月形にし、裏返して軽く焼く。
ポイント 行者ニンニクは軽く熱を通すほどがおいしい。
2006年3月11日付紙面掲載