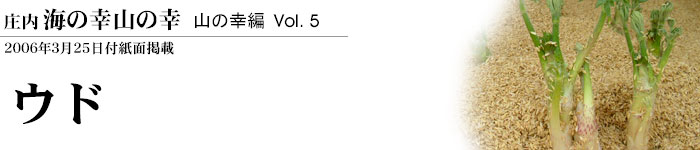- 音声ブラウザをご利用のお客様向けのリンクです。
- 本文へジャンプする
独特の香気が深山の幸を感じさせるウドは全国に広く分布し、古くから栽培も行われてきた。旧八幡町は、町のシンボルだった鳥海山にちなんで「鳥海うど」の名でブランド化を図った。ハウス栽培、露地栽培のウドは、自生のヤマウドとひと味違うくせのなさが支持され、産直施設「たわわ」の春を代表する人気商品に定着した。
「今シーズンは、年末の大雪で株を全部ハウスに移す時間がなかったんです。栽培量も少ない上に厳冬でなかなか成長せず、収穫も遅れてしまいました」。たわわでウドを販売している本多京子さんが苦笑いする。例年なら2月中旬に収穫が始まるが、今年はたわわへの初登場は3月7日。3週間近くずれ込んだ。
本多さんは5年ほど前、会社勤めを辞めたのを機にウドのハウス栽培を始めた。株分けから出荷するまで2年近くを要し、2度の夏を越さなければならない。「除草剤を使わないので夏の草取りが大変ですが、愛情を込めて育てています」と話す。

自宅そばのハウスに入ると、ウド特有の山の香りが広がる。もみ殻から緑色の穂先が顔を出せば収穫期で、もみ殻に隠れている部分は白色。がっしりしていてモヤシウドという表現が当てはまらないたくましさを備えている。根元を鉄製の器具で切り落とし、エアを吹きかけ、汚れを落としてから出荷する。
あくの強い天然のヤマウドに比べ、モヤシウドは香気の面では劣るが、ハウス物は露地栽培のウドより食べやすい。「見た目では区別がつかないと思います。ヤマウドが嫌いな人でもハウス物なら大丈夫。私はくせがないハウス物が一番好きです。水にさらして生でみそを付けたり、きんぴらや天ぷら、ゆでて酢みそ和え、酒かすを加えてみそ汁、ニシンとの炊き合わせと、いろんな料理にして食べてください」とPRする。
本多さんがびっくりしたというのがウドを使ったかき揚げ。「ある旅館のメニューで見て、自宅に帰ってからウルイ、短冊切りしたナガイモと一緒にかき揚げにしてみました。揚げたてがすごくおいしかったです」と話す。
「たわわには「『昨日買ったらおいしかったのでまた来た』という人もいます。ウドをあげると『ごっつぉだのう』と喜んでもらえますが、『買ってまで食べなくともいい』と思う人もいるようです。でも私なら買ってでも食べたいと思います」と言うほどウドにほれ込んでいる。
たわわでは2~7本入った450~500g入りを1袋315円で販売している。ハウス栽培のウドは4月中旬まで店頭に並び、20日ごろから露地物に切り替わる。5月10日以降は天然のヤマウドが加わり、「出羽富士」の大地がはぐくむ自然の恵みが人気を集める。
本田さんのおすすめレシピ
ウドの粕漬け
○材料
ウド、塩、砂糖、酒かす
○作り方
- ウドをきれいに洗い水切りし、皮をむいた後、長さを3cmほどに合わせて切る。
- 水に半日ほどさらしてあく抜きする。
- 樽に好みの量の塩と砂糖、酒かすを入れてウドを並べて漬ける。樽の代わりにボウルでも可。3日ぐらいたったら食べごろ。
2006年3月25日付紙面掲載