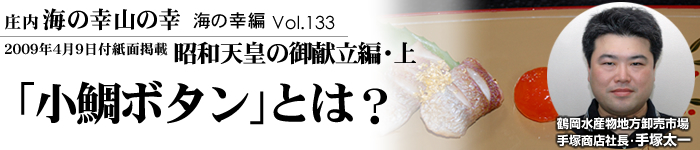- 音声ブラウザをご利用のお客様向けのリンクです。
- 本文へジャンプする
読者から「昭和22年8月15日、昭和天皇が戦後復興の視察で鶴岡市を訪問された際、旧庄内藩主の酒井家に一泊されました。その時、酒井家では庄内の郷土料理をお出ししたそうです。その中でお魚が関係した料理を再現できないでしょうか」という質問をいただきました。
大変な難題です。魚ならともかく、料理の再現などわたしの手に負えるものではありません。鶴岡魚市場に毎朝、顔を出す日本料理店「暫忻亭(ざんきんてい)」(鶴岡市本町三丁目)の若主人・木曽眞さんに相談したところ、「天皇陛下が召し上がった料理をぜひ作ってみたい」と力を貸してくれることになりました。今回はわたしと木曽さんの合作です。
まず、当時の献立表を調べてみました。公式に残っているものは見つからず、荘内日報の前身である荘内自由新聞が「御泊所の御献立」の見出しで献立表と陛下のご様子などを報じていたことが分かりました。当時、料理に携わった方にお話を聞くことができればいいのですが、故人となっている方も多く、かないませんでした。荘内自由新聞の献立表をもとに、当時の食糧事情も考慮しながら、料理の再現に挑戦してみました。「完全版」とはいかないかもしれませんが、ご容赦ください。

「御座付(ござつき)」として最初に出てきたのが枝豆です。8月15日に白山だだちゃ豆が出ていたかは微妙ですが、鶴岡が誇るおいしい枝豆が陛下の口に入ったことでしょう。「御椀(おわん)」は若鶏をメーンにしたお吸い物です。「季節からして筍は月山筍だろう」と木曽さんは言います。
「作り身」は刺し身です。養老海老という種類のエビはいません。真夏のエビと言えば、クルマエビが思い浮かびますが、舟盛りにしたというのでシマエビを使うことにしました。シマエビは、庄内浜ではめったに捕れませんが、以前は網にかかっていたかもしれません。62年前の料理に登場した可能性はあると思います。夏らしく大葉、つまり青ジソの千切りとミョウガが添えられたのでしょう。
でも、木曽さんが作った料理は単純な刺し身ではありませんでした。本人に解説してもらいましょう。
「刺し身とはいえ、生のまま陛下にお出しすることはないと思います。火を通したはずです。さっとお湯にくぐらせ、冷水で締めた湯引きという料理法を採用しました」。湯洗いとは湯引きのことだったのですね。
次の「口取」が難関でした。コダイはチダイの子。タイの子のタイコとは別物です。コダイは夏が最もおいしいのです。木曽さんは、「小鯛ボタン」をコダイの塩焼きと黄金卵と解釈しました。黄金卵とは卵黄を西京味噌に漬け込み、黄金色に仕上げたものだそうです。「黄金卵を服のボタンに見立てたのではないでしょうか。卵は当時、高級品でした。天皇陛下をもてなす食材に選ばれても不思議はありません」という木曽さんの解説に納得しました。
次の「百金木(ひゃっきんこ)の葉玉子(はたまご)」の解釈にさらに頭を悩ませました。どこで区切るかで、意味も変わってくるからです。最初は「百金木」の「葉玉子」かとも思ったのですが、百金木という木はありませんでした。そこで「百金」「木の葉玉子」と分けてみました。「木の葉玉子」なら黄身と白身に分けて蒸した「二色卵」を木の葉の形にしたものだろうと木曽さんが考えたのです。では「百金」は何か。「陛下をお迎えしたおめでたい席なので、金粉、または金箔(きんぱく)を使ったのでは」と木曽さんは推理し、金粉をコダイの塩焼きに散らしたのです。そして「小鯛ボタン百金木の葉玉子」が完成しました。紙数が尽きました。次回も昭和天皇の献立を再現します。
〔献立表〕
御座付 枝豆塩茹(えだまめしおゆで)
御椀 若鳥(わかどり)、椎茸(しいたけ)、筍葱(たけのこねぎ)、荘内麩(しょうないふ)
作り身 養老海老湯洗舟盛(ようろうえびゆあらいふなもり)、線紫蘇(せんしそ)、茗荷(みょうが)、山葵土佐醤油(わさびとさじょうゆ)
口取 小鯛(こだい)ボタン百金木(ひゃっきんこ)の葉玉子(はたまご)
鉢肴 甘鯛肉(あまだいにく)けんちん焼、含(ふく)め栗(ぐり)、日の出正賀(でしょうが)
煮物 鯛(たい)オランダ煮、なめ子、芽の子
中皿 アワビ福羅煮(ふくらに)、茄子
丼 胡麻豆腐、餡正賀(あんしょうが)
酢の物 契(ちぎ)り海老、外野菜、久留美合(くるみあ)へ
香の物 民田茄子一夜漬(みんでんなすいちやづけ)、黄金漬(こがねづけ)、瓜味噌漬(うりみそづけ)
御飯
水菓子 水瓜(すいか)、水蜜桃(すいみつとう)
(鶴岡水産物地方卸売市場手塚商店社長・手塚太一)
2009年4月9日付紙面掲載