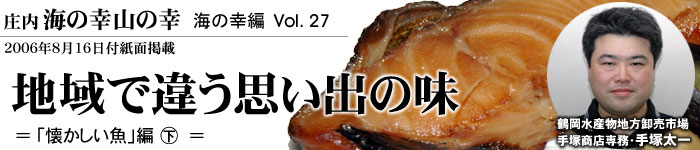- 音声ブラウザをご利用のお客様向けのリンクです。
- 本文へジャンプする
年配の人に聞いたのですが、今は帰省シーズンに旅館が満員になりますが、昔はがらがらだったそうです。うちの社長の話では、昔からお盆のころは、水産物はよく動きました。地元の人は帰省客に魚を食べさせたいと思っているし、帰ってくる人も都会では手に入らない地物の魚を食べたいということなのでしょうね。
季節はちょっとずれますが、以前にこのコーナーで取り上げたカナガシラとイワシも最近はあまり食べなくなってきた魚です。イワシは大発生と衰退を繰り返してきた魚で、あまり捕れなくなった今は高値になったということもあるでしょう。
ギンダラも「好きなんだけど食べなくなった」と言われる懐かしい魚になってしまいました。これも価格が上がったということがあるでしょう。昔は「外国の人が捕って日本人が食べる」という感じでしたが、今は中国をはじめとした各国で食べるようになりました。日本人がうまいと思うものを外国の人も食べる。食に国境はないということでしょうか。
庄内の人にとってギンダラのしょうゆ漬けは東京では食べられない懐かしい味なのかもしれません。以前は100円/gで売っていたのが今は200円出しても買えない。帰省したらギンダラを食べたいという人はけっこういるのではないでしょうか。
棒だらやカスベなどコトコトと煮るもの、シノコダイなど甘辛くして食べるもの、つまり手間暇かけるものも食べなくなりました。食文化も変わりつつあります。鮮魚店でも焼き物や刺し身はやりますが、昔のお母さんが作っていたような家庭料理は売っていません。おふくろの味はなくなりました。ある魚屋さんは「おふくろの味が袋の味になってしまった」と言っていました。スーパーなどで袋に入ったものをお母さんが買ってきて食べさせる。今の時代を象徴している話だと思います。
懐かしい魚には地域性も表れると思います。海側と山間部では違います。先の話は市街地のことと考えてください。山間部には流通が発達する以前、なかなか水産物は行き渡りませんでした。干物とか粕漬けなど加工したものが多く、生の魚の場合はたくさん捕れたハタハタやニシンなどを箱ごと買ったりしたそうです。箱単位で買っても値段は安かったでしょう。そしてしょうゆ漬けや唐揚げにしたりして、なくなるまで毎日、いろんな料理が食卓を飾ったのです。

一方、海岸部では魚は毎日食べるのが当たり前でしたし、残り物ではなく、食べたいものを食べていたようです。地域によって懐かしい魚というのは変わってくるものです。
今回は、2回に分けて懐かしい魚を取り上げました。記憶の彼方にある魚も今ではなかなか食べられなくなってしまいました。いつかまた、「懐かしい魚」が手ごろな値段で食べられる時が来るといいですね。
(鶴岡水産物地方卸売市場手塚商店専務・手塚太一)
2006年8月16日付紙面掲載