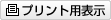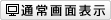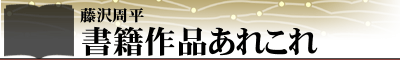- 音声ブラウザをご利用のお客様向けのリンクです。
- 本文へジャンプする
「竹光始末(1)」 からのつづき

ところが藩主忠直の横暴に逆らって吉田家の主が切腹して果てる事件があり、丹十郎はまたしても浪人する羽目になる。そして、海坂藩で新規召し抱えがあるという情報をもとに、はるばるとこの北国へやって来たのである。ところが、またしても不運なことに、海坂藩では新規召し抱えはとうに終わって人手は不要だったのである。この間の悪さには、滑稽(こっけい)感さえついてくる。悲劇的滑稽感というような。作者はこのことを「芝居の幕が下りてから大真面目で舞台に出てきた役者をみるような、滑稽」さだ、と述べている。他の作品でもこのような間の悪い、格好(かっこう)悪い武士が登場する。「玄鳥」の曽根兵六や「潮田伝五郎置文」の伝五郎など、歯がゆいほどの間の悪さのため、自滅に追い込まれたりしている。
小黒丹十郎は海坂藩の城下で困窮して暮らしている。宿代も払えず、ついに刀を売ってしまった。竹光となった武士の魂。そこにさらに間が悪く、1人の男の上意討ちの話が舞い込む。その男の名は余語善右衛門といい、この間の新規召し抱えで採用されたばかりだったのに、上司と衝突した揚げ句、藩主の怒りを買ってしまったという。うまく討ち取れば70石の禄でやとおうという海坂藩。竹光でどう闘うのであろうか。
こんな悲劇的な話なのであるが、この小説の印象は暗くない。ほのかな温かみやユーモアさえ感じられる。その理由は丹十郎の人柄と、妻子の存在であろう。妻と2人の娘は丹十郎を信じ切っている。どんな時も飢えさせず、自分たちを守ってくれる男として全幅の信頼を寄せている。4人はぼろをまとっていても心は凛(りん)としていて安らかなのである。妻の多美は「お前さまも、苦労されますなぁ」と呟(つぶや)くことはあっても、暮らしに不満をもらしたりしない。多美は幼い時に両親を失い、小黒家に引きとられたのであり、頼る人は丹十郎だけなのである。実は「たそがれ清兵衛」の妻・奈美も同じような境遇で清兵衛1人にすがって生きている。こちらの夫婦には子供はいないが、似たような家族である。
さて、小黒丹十郎が対決したのは、越後の村上藩に仕えていたが元和4年に村上9万石がとりつぶされて以来、10年も浪人した男だった。ここにも1人、非情な幕命の下に右往左往させられる武士がいた。主に仕える者としてやむなき運命なのだが、切る者も、切られる者も辛(つら)い。小黒丹十郎は「武家というものは哀れなものだの」と心の中で呟くのである。似たテーマの作品「遠方より来たる」や「証拠人」などと併せて読んでほしい作品である。
- たそがれ清兵衛(松竹公式サイト)