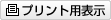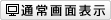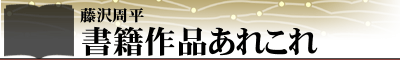- 音声ブラウザをご利用のお客様向けのリンクです。
- 本文へジャンプする

「文四郎ははだしで、菜園の茄子に水をやっていた。茄子畑は菜園の隅のたった三畝だけだが、まだ紫の花をうけ、つややかな色をした実がいっぱいなっている。」
これは『蝉しぐれ』の第二章「夜祭り」の冒頭の一節である。晩夏の夕方、まだ熱気の残る畑に水をやるため、文四郎は小川と茄子(なす)畑の間をいく度も往復し、汗みずくになる。茄子畑ほど水を吸う畑はない、と思いながらも、皮の柔らかい、うまい茄子を得るため、せっせと桶(おけ)に水を汲(く)むのである。
この光景は藤沢さんの少年時代の経験が反映されていて実感がこもっている。夏の間、畑に水かけをするのは子供の役目だった。朝と夕方の2回、たっぷり水をやると茄子は毎日ザルにいっぱいとれ、食卓はそれこそ茄子づくしになる。一夜漬け茄子の藍(あい)色。へたをとるとそこだけ白く、その鮮やかな対比、そしてプチッと噛(か)んだときの歯ごたえ。これは夏の間の楽しみである。茄子ゆで、茄子いため、焼き茄子、はては生のまま細かく切って、胡瓜(きゅうり)やシソの葉を入れ、冷水に味噌(みそ)をといただけの冷汁。忙しい農家の昼食にも茄子は重宝がられた。私も茄子の水かけをしていて、ぬれた土手で転び、汗に涙、水と泥でぐしゃぐしゃになったことを覚えている。子供が1回で運べる水の量では、茄子の3株ぐらいを潤すだけなので、水をかけ終わるころは本当に茄子など見たくもないと思ったものだ。このように丹精こめて野菜を作り、家族に食べさせるのは主として女性の仕事であった。
「菜園のある屋敷(2)」へつづく
(筆者・松田静子/鶴岡藤沢周平文学愛好会顧問)
Loading news. please wait...