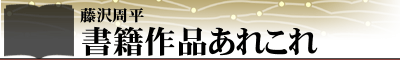- 音声ブラウザをご利用のお客様向けのリンクです。
- 本文へジャンプする
「欅のある風景(1)」 からのつづき

人間は年を経るほどに身にまとうものが多くなり、それらを振り捨てることは難しくなる一方だ。きれいさっぱり落とし尽して死ぬ人間はいないだろう。実際、孫左衛門にもこの後、隠居どころではない騒動が降りかかってくる。あらん限りの知恵と力でそれを解決した後、孫左衛門には、孫が出来る。欅の木も新芽をつけ、春光の中で柔らかく光っているのを見ながら、孫左衛門は「生きていれば、よいこともある」とつぶやくのである。
欅の木は、藤沢さんの生まれた村にも多い。農家では、風よけの木として欅を植え、その木を中心に雪囲いをしたりした。役に立つ木の1つだった。集落全体を欅が包んでいる光景も庄内ではよく見られる。『蝉しぐれ』に登場する「欅御殿」はそんな風景だろうと思われる。そういえば、半藤一利氏が鶴岡を探訪されたとき、「欅御殿」のある場所は、高坂じゃないですか、と仰(おっしゃ)っていた。地理的にもぴったりで、文四郎たちが舟で逃げる川も青龍寺川らしい、と言われたのを思い出す。
このように欅は私たちの町になじんできた木であるが、最近、この木を嫌う人が増えているという。落葉が多く、隣近所に飛ぶので苦情も多いそうだ。落葉焚(た)きも何かと問題があってままならぬ昨今、ゴミが多いと欅がヤリ玉にあげられる、困った、と樹齢100年以上はなろうという大木を、処分しようか、どうか迷っているお年寄りの話を聞いた。他にも、都会では、鳥の棲家(すみか)となるため、フンが落ちて困ると、枝という枝をバッサリ切った町もあるという。悲しい話だ。木工用にも使われることが少なくなって、欅はだんだん消えるのだろうか。人間の思惑をよそに、冬の欅は静かに立っている。
(筆者・松田静子/鶴岡藤沢周平文学愛好会顧問)
Loading news. please wait...