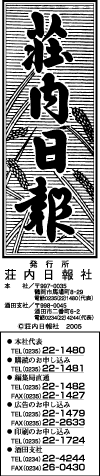- 音声ブラウザをご利用のお客様向けのリンクです。
- 本文へジャンプする
荘内日報ニュース
2024年(令和6年) 7月28日(日)付紙面より
ツイート鶴岡東に栄冠 夏の甲子園へ2年ぶり8回目 夏の高校野球山形大会
鶴岡東が2年ぶり8回目の甲子園―。第106回全国高校野球選手権山形大会は27日、中山町のヤマリョースタジアム山形(県野球場)で決勝が行われ、第1シードの鶴岡東と第2シードの山形城北が甲子園行きの切符を懸けて激突した。相手の失策も重なり鶴岡東が5回までに大量リードを奪って試合を優位に進め11―1で勝利。2年ぶりに山形大会優勝の栄冠を手にし、夏の甲子園大会出場を決めた。甲子園大会は8月4日(日)に組み合わせ抽選会を行い、8月7日(水)に兵庫県西宮市の阪神甲子園球場で開幕する。
先攻の鶴岡東は初回、無死一、二塁で日下の打球を一塁手が悪送球し1点先制。その後1死一、三塁で小林の左前打で2点目を入れた。4回は相手バッテリーエラーで1点を追加。5回は小林の安打と億田のバントヒットと悪送球で無死一、三塁とし、酒井が左前にタイムリーヒット。さらに無死満塁で、杉浦が中前に弾き返し、1点を追加。続く丹羽のセカンドゴロでダブルプレーを狙った送球が乱れ、2者がかえってこの回4点を挙げ、前半で7―1と大きくリード。6回に1点、7回に2点、8回に1点を挙げ、突き放した。先発の杉浦は初回に犠飛で1点を失ったものの、2回以降は3安打に抑え、勝利を呼び込んだ。
2024年(令和6年) 7月28日(日)付紙面より
ツイート泥かき出しに追われる 酒田 床上・床下浸水50件超 大雨被害
26日朝にかけて大雨に見舞われた庄内地方は27日、住民が浸水の後片付けに追われた。28日にかけ梅雨前線が再び東北地方を北上し、大気の状態が非常に不安定となる見込みで、山形地方気象台は引き続き土砂災害、浸水に厳重に警戒するよう呼び掛けている。
2度にわたって大雨特別警報が出された酒田市のうち、荒瀬川が氾濫したため甚大な被害が出た八幡地域では一時、大沢地区が孤立。陸上自衛隊神町駐屯地(東根市)から第20普通科連隊が出動し、地区住民の救助に当たった。国道344号は八幡総合支所以東で通行止めの措置が続く。荒瀬川から泥水が流れ込んだ八幡保育園では、住民らがかき出す作業に追われ、断続的な降雨で中断を繰り返しながら汗を流していた。
同市の26日午後7時までのまとめによると、人的被害の報告はない。建物の浸水被害は床上・床下計51件と、八幡地域の市営アパート12棟で確認しているほか、袖浦川が越水したため錦町地内でも発生している模様。八幡・平田両地域では断水している。停電発生箇所もある。
市は27日、災害復興支援に向けた寄付の受け付けを各ふるさと納税サイトで始めた。災害支援のため返礼品はない。酒田市民も申し込みでき、全額を復旧事業、今後の防災対策に活用する。
同じく大雨特別警報が出された遊佐町では27日から、家庭から出た災害ごみの受け入れが始まった。サン・スポーツランド遊佐(小原田)、あぽん西浜南側(吹浦)の2カ所で午前9時から午後4時まで受け付けている。
2024年(令和6年) 7月28日(日)付紙面より
ツイート人口減の打開策は 庄内総合高生と役場職員意見交換 若者の意見参考に何ができるか考える
庄内町の庄内総合高校(佐藤りか校長)で23日、「少子化対策意見交換会」が開かれ、3年生11人が町役場職員らと意見を交わした。同校の「地域を学ぶ」という選択授業の一環。同町では人口減少が顕著で、特に女子中高生の人口が20年前と比べほぼ半数しかいない状況。町にいる若者の意見を参考に人口減少の打開策を探ろうと、意見交換会を実施した。
この日は町企画情報、子育て応援両課職員4人が同校を訪問。▽町の特徴や魅力▽町に住み続けたいと思うか▽若者が住み続けるために町にしてほしいことは―をテーマに生徒たちに意見を募った。
生徒たちは「自然が豊か」「食材がおいしい」「庄内金魚がかわいい」など町の魅力について述べる一方、「進学のため県外を目指すが、戻って来たいか今は分からない」「やりたい仕事や専門職に就くための学校が町内にない」「結婚相手によって県外に行くかも」など将来的に町外へ出ることや、町内で希望職に就くことの難しさを語った。
また「一度は県外に出たいが、最終的には町に戻ってこれたら。その時に住みやすくなっていたらうれしい」などの意見もあり、職員たちは熱心にメモを取りながら、多くの意見に耳を傾けていた。
参加した齋藤凌玖(りく)さん(18)は「庄内町を深く知るきっかけになった。自分は町に愛着を持っているので、卒業後も住み続けていけたら」と。町企画情報課の伊藤典子主任は「実際に聞かないと分からないことが多くあった。皆さんの意見を参考に、町として何ができるか考えていきたい」と話した。
2024年(令和6年) 7月28日(日)付紙面より
ツイートSDGsの絵本通し未来考える 鶴岡市立図書館 読書案内人・本間さんが紹介と解説
SDGs(国連の持続可能な開発目標)にまつわる絵本を通して未来を考える講座が20日、鶴岡市立図書館で開かれた。
今年で結成20周年を迎えた鶴岡市の市民団体「子どもの読書を支える会」(戸村雅子代表)が主催する「子どもの本・学びの会」の本年度第2講座。元小学校校長で、読書案内人として活躍している本間俊美さんが「絵本からSDGsを~小さな問いから未来をのぞこう~」をテーマに語った。
SDGsとは環境問題や差別、貧困、人権問題などの17の課題に取り組む開発目標。会場には市立図書館の協力でゴールごとに関連する書籍を表示して展示したほか、支える会の担当者がSDGsに関するクイズを出題。加盟している国は世界の90%以上であることや日本の子どもの9人に1人がその日の食事に困っていること、鶴岡市でSDGsを推進している企業や団体は120余りに上ることなどを解説した。
講演で本間さんは、レオ=レオニの有名な絵本『スイミー』を取り上げ、「この本は小さくても力を合わせれば生きていけることがテーマだと思っていたが、実はSDGsがあふれる壮大な本だった」とし、仲間と自分が違うことに気づくこと(ジェンダー平等の実現)や仲間を探した時に出会った海の生き物の多様性(海の豊かさを守ろう)、自分がどう動けばいいかを考えてみんなと一緒に頑張る(パートナーシップで目標を達成)などが盛り込まれていることを紹介。「みんなに役割があり生きていることを地球規模で考えようと作者は伝えたかったのでは。これからも絵本からSDGsを読み解いていきたい」と話した。