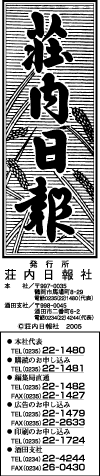- 音声ブラウザをご利用のお客様向けのリンクです。
- 本文へジャンプする
荘内日報ニュース
2023年(令和5年) 12月5日(火)付紙面より
ツイート“最後の農家”母から継承 地域の宝「宝谷かぶ」守り続ける 畑山峻さん(24)担い手に 伝統野菜絶やさないよう頑張る
鶴岡市宝谷の農家・畑山千津さん(44)が地区の伝統野菜「宝谷かぶ」を守り続けている。栽培の難しさや収量にばらつきがあり、作る農家は年々減少。高齢化と担い手不足も追い打ちをかけ、今では畑山さん1軒だけとなった。宝谷かぶの“最後の農家”となったが3年前に息子の峻さん(24)が担い手に。「宝谷で育った一人。地域の『宝』をなくすわけにはいかない」と継承に意欲を見せている。
宝谷かぶの大きさは直径4、5センチ。例年8月のお盆過ぎに焼き畑で種をまき11月下旬に収穫を迎える。連作障害の影響を受けやすく1年ごと場所を変えなければならない。天ぷらや煮物のほか、「そのまますりおろしてそばつゆに付け、辛味を味わうスタイルが一番おいしい」というファンも多い。
2006年に宝谷かぶを守ろうと、鶴岡市櫛引庁舎の職員やアル・ケッチァーノの奥田政行シェフ、山形大学農学部の江頭宏昌教授が中心となり「宝谷蕪主(かぶぬし)会」を立ち上げた。一口7000円でオーナーとなり、収穫体験を楽しみながらカブをもらえるという仕組み。一時は人気を集めたが、栽培農家に押し寄せる高齢化の波には勝てなかった。すでにオーナー制度は発展解消。残った畑山さんがボランティアの協力を得て育てている。
農作業をする祖父・丑之助さん(92)の姿を見て自然と栽培のポイントを覚えたという千津さん。「特に宝谷かぶは天候によって左右される。今年のように日照り続きだったり、長雨でも駄目。適度な斜面で水はけが良くないと育ってくれない。宝谷の土壌も適しているのだと思う」と話す。
2021年には県立農林大学校(新庄市)を卒業した長男の峻さんが実家の農業を継いだ。すでに中学生の頃に継ぐ意思が固まっていた峻さんは「ごく自然に宝谷かぶを守ることが自分の役割と思っていた。稲作と花きが中心だが、豊かな環境の宝谷で農業を続ける大切さも感じていた。絶やさないよう頑張りたい」と決意を語る。
高温少雨が心配されたが先月下旬には約350キロのみずみずしい宝谷かぶが採れた。
今年も料理の面から在来野菜のアピールと維持に向けてバックアップしているアル・ケッチァーノや出羽三山神社の斎館、市立加茂水族館魚匠ダイニング沖海月のほか、寿司てんぷら「芝楽」に納めた。
千津さんは「地域の温かい協力があるからこそ(宝谷かぶを)栽培することができる。カブを買ってくれるお店にしても、焼き畑や収穫を手伝ってくれるボランティアの方々には本当に感謝の気持ちでいっぱい。これからも息子と共に作り続けていきたい」と笑顔を見せた。