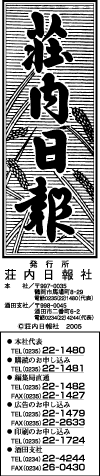- 音声ブラウザをご利用のお客様向けのリンクです。
- 本文へジャンプする
荘内日報ニュース
2025年(令和7年) 5月7日(水)付紙面より
ツイート藤の花咲き始める 10、11日藤島地域「ふじの花まつり」
鶴岡市の藤島地域で藤の花が咲き始めた。10、11の両日は東田川文化記念館と藤島歴史公園Hisu花を主会場に「ふじの花まつり」が開かれる。
「ふじの花まつり」は今年で34回目。ふじしま観光協会や出羽商工会、藤島芸術文化協会、JA庄内たがわ藤島支所などで実行委員会を組織し、藤の花が見頃になる時期に合わせて多彩なイベントを企画している。
今年も東田川文化記念館で恒例の「ふじの花盆栽展」や「ふじの花芸術文化展」「俳句大会」「むかし話語り」、藤島歴史公園Hisu花ではキッチンカーが集合した「ふじの花マルシェ」、親子を対象にしたアドベンチャーゲーム、藤の管理講習会などを繰り広げる。
初日の10日午後7時半からは「第32回赤川花火大会・鶴岡市制施行20周年記念事業」として花火を打ち上げ初夏の夜空を彩る。歴史公園の藤棚は今月3日からライトアップ(午後6時半から同9時)が始まった。
藤島体育館のグラウンドゴルフコースそばにある藤棚は、ようやく咲き始めたばかり。好天となった5日は連休中の行楽客が訪れ、紫色に咲いた藤をバックに記念撮影する姿が見られた。天候にもよるが、まつり当日には見頃を迎えそうだ。
「ふじの花まつり」に関する問い合わせは実行委員会事務局のふじしま観光協会=電0235(64)2229=へ。
2025年(令和7年) 5月7日(水)付紙面より
ツイート五穀豊穣願い伝統紡ぐ ササラ響かせ花笠舞 鶴岡 民俗芸能「高寺八講」
鶴岡市羽黒町高寺の雷電神社(松平修宮司)に伝わる民俗芸能「高寺八講」(県指定無形民俗文化財)が4日、同神社の春例祭で奉納上演された。大勢の見物客が訪れ、五穀豊穣(ほうじょう)を祈る演舞に見入った。
高寺八講は鎌倉時代の古典芸能の流れをくむ貴重な古典芸能として、1976(昭和51)年に県の文化財に指定された。「八講」の名称は、法華経の講義を意味する「法華八講」に由来するといった説や、「演目がかつて八番あった」など諸説ある。明治時代半ばまでは現在より多くの演目があったというが、今は4演目を伝承している。
子どもから大人までの演者らが地区内を練り歩き、神社拝殿で祈祷(きとう)を受けた後、境内の八講楽殿に上がり、勇壮な「薙刀(なぎなた)舞」や全国でも一部でしか舞われていない貴重な「大小舞」が披露された。メインの「花笠舞」は、色鮮やかな花を差した四角い花笠をかぶり、ササラや扇を手にした6人の舞い手が独特の所作で豊作を願う田楽舞を奉納した。
「ジャッ、ジャッ」とササラの音が響く中、境内を訪れた地元住民らが舞台を見つめ、大勢のアマチュアカメラマンが盛んにシャッターを切っていた。最後に子どもたちによる稚児舞も行われた。
隣接する下馬渡地区から3歳の息子ら家族で訪れた小林亮大さん(38)は「近所の子どもが稚児舞に出るので初めて見に来た。華やかな舞を高寺地区でずっと守り伝えてきたことに驚いた。息子もいずれは稚児舞を舞うことになると思う」と話していた。
2025年(令和7年) 5月7日(水)付紙面より
ツイート元気な歓声響く 「酒田市子どもまつり」楽しむ
酒田市子どもまつりが5日、同市の日和山公園をメイン会場に開かれ、柔らかな日差しが降り注ぐ中、元気な子どもたちの歓声が青空に響いた。
次代を担う子どもたちの健全育成を目的に、市、市子ども会育成連合会(市子連)など計14機関・団体・企業が実行委員会(須田文男実行委員長)を組織し「子どもの日」に合わせ開催。71回目を迎えた今年は消防、警察、自衛隊による「働く車」乗車体験のほか、わんぱく相撲、遊びながら学べるジオパークコーナーといったイベントが目白押しで、大勢の家族連れが集まった。
このうち、市子連(齋藤学会長)が主催する魚のつかみ取り「ざっこしめ大会」には大勢の子どもたちが参加。特設プールに入った就学前の幼児たちは、「スタート」の合図で一斉に濡れるのも構わず金魚やフナを追いかけた。参加した酒田市東泉町四丁目の小笠原明里ちゃん(4)は「大きな魚が取れて楽しかった」と笑顔で話した。
2025年(令和7年) 5月7日(水)付紙面より
ツイート公益大の入学者が開学後最多に
東北公益文科大学の2025年度の学部入学者が294人(編入7人を含む)で、開学以来最多となった。全国的に地方の私立大学で定員割れが続く中、社会情勢の多様化から、「公益学」に対する理解が深まっているためであろう。まずもって定員超えを喜びたい。この先も他に誇る事ができる大学にしたい。その役目を担うのは学生ではないだろうか。
公益大は26年4月の公立化・機能強化に向けた準備が進んでいる。学生は地元や県内、東北地方だけでなく関東・甲信越、九州地方など全国各地から集まった。開学から四半世紀を迎えようとしており、着実に知名度が高まってきた証しであろう。
◇ ◇
24年度は入学者が定員割れした私立大学が全国で約6割に達したという。先頃、京都ノートルダム女子大学(京都市)を運営する学校法人が、26年度以降の学生募集を停止すると発表した。学生が在籍する間は教育を続け、29年3月で閉学するという。少子化によって、大都市の大学でも学生確保が難しくなっている現実の一端の中での、公益大の健闘ぶりである。
公益大の公立化は長年の懸案だった。しかし、それだけで経営環境が改善するとは限らない。大学の特色ある教育内容によって学生を引き付けなければならない。公益大は13年度の「地(知)の拠点整備事業」を皮切りに、大学教育再生戦略推進費「大学教育再生加速プログラム」、学長のリーダーシップで大学の特色ある研究で全学的な独自色を打ち出す「私立大学研究ブランディング事業」、組織を挙げて改革に取り組む私立大学を重点的に支援する「私立大学等改革総合支援事業」と、相次いで文部科学省の採択・選定を受け、公益学ならではの魅力ある大学づくりに取り組んできた。
大学進学では依然として中央志向がある中で、中央への進学が厳しい受験生もいる。地方から大学が減れば、そうした受験生が影響を受ける。公益大は文科省の採択でさまざまな教育を取り入れていることを最大限活用し、教育内容の質向上と学生確保、経営健全化につなげていきたい。
◇ ◇
文科省は私立大の経営安定に向け、経営改善を目指す学校法人を指導し、学部新設の審査基準も厳格にするという。経営が悪化傾向にある法人は、状況が改善しなければ募集停止、法人解散の判断を促すとされる。その点、公益大は文科省の採択でさまざまな教育を取り入れながら、定員を確保していることは評価されるのでないか。
25年度入学式で、新田嘉一理事長は「公益大の魅力と評価が高まっている。大学の学びを通じて何にでも挑戦してほしい。失敗しても社会はみなさんを応援してくれる」と新入生を励ました。新田理事長の言葉を借りれば、学生一人一人の挑戦の成果が、この先の公益大のさらなる基礎を固めていくことになる。
2025年(令和7年) 5月7日(水)付紙面より
ツイート重さ16キロの薬師如来像を山頂神社へ 酒田市の田沢地区 「胎蔵山背負い上げ」健康祈る
酒田市田沢地区の薬師神社本殿から胎蔵山(標高729メートル)山頂の同神社「奥の院」まで、御神体の薬師如来像(混合銅製、高さ約40センチ、重さ約16キロ)を背負って運び上げる神事「胎蔵山背負い上げ」が3日、胎蔵山で行われ、参加者が一年の健康などを祈りながら山頂を目指した。
胎蔵山は約1200年前に弘法大師が開山し、古くから山岳信仰の山として親しまれてきた。昔は山頂に神社本殿があり、中に黄金色に輝く薬師如来像を御神体として安置していたが、100年以上前に盗難事件が発生。新たな御神体を作る際に「地元民の目が届くところに」と、麓の田沢集落に本殿を移築した。そして山頂の本殿を「奥の院」として、年に1度御神体を山頂まで運ぶ神事が行われるようになったという。現在は地元の地域活性化に取り組む「胎蔵ロマン会」(岩間政幸会長)が中心となり、交代で背負い役となる参加者を広く募り実施している。
この日は会員を含め県内外から計44人が参加。周囲の木々に前日降った雨粒が残る中、午前7時に同神社の佐藤共子宮司が道中の安全などを願い祈祷(きとう)した後、参加者たちに「自身の心とも向き合いながら背負ってもらえたら」と見送りの言葉を送った。
神社から下ろした御神体と共に2キロほど離れた胎蔵山登山口まで車で移動。だんだんと晴れ間がのぞく中、一行は背負子(しょいこ)と合わせて約20キロにもなる御神体を代わる代わる背負い、ホトトギス、ヤマゲラ、シジュウカラなど野鳥の声が飛び交う登山道を進んだ。
道中、鳥居松や中の宮で休憩を取り、足元にかれんに咲くスミレ、ショウジョウバカマ、ヒトリシズカ、カタバミといった色とりどりの草花に元気づけられながら、午前11時ごろ「奥の院」に到着。1年ぶりに鎮座した御神体に、参加者や集まった登山客らは恭しく手を合わせ、無病息災などを祈願した。
初めて参加したという遠藤円(まどか)さん(48)=同市中牧田=は「松山地域からいつも眺めていて、いつか登りたいと思っていた。御神体は重かったが、良いことがありますようにと願いながら背負った」と笑顔で感想を話した。
2025年(令和7年) 5月7日(水)付紙面より
ツイートダンスと演奏 趣向凝らしたステージ 致道館高校吹奏楽研究会定期演奏会 会場埋めた観客を魅了
致道館高校吹奏楽研究会(吹研、佐藤杏紗会長、会員57人)の第2回定期演奏会が5日、鶴岡市の荘銀タクト鶴岡で開かれた。2025年度全日本吹奏楽コンクール課題曲の勇壮なマーチ(行進曲)や、ダンスと演奏のステージなど趣向を凝らした演出で、会場を埋めた観客を魅了した。
会場には市民や中学、高校の吹奏楽部員、致道館高の前身で統合した鶴岡南、鶴岡北のOB、OGなど約900人が足を運びほぼ満席となった。
ステージは2部構成で、第1部は中高一貫校の致道館中学・高校の校歌演奏でスタート。本年度の全日本吹奏楽コンクール課題曲「マーチ『メモリーズ・リフレイン』」などを披露した。
第2部は、かつて東京ディズニーランドの夜を飾ったパレード「ディズニー・ファンティリュージョン!」の演奏に乗せ、ディズニーキャラクターの扮装をした1年生たちがダンスを披露。また、トロンボーンやサックスのソロ演奏、1960~70年代を代表するハードロックバンド「ディープ・パープル」のメドレー演奏なども行われ、趣向を凝らしたステージに来場者が大きな拍手を送った。
アンコールは鶴南吹研時代からの定番で、吹研OBの真島俊夫さん(1949~2016年)編曲の「宝島」を演奏。楽しく演奏する高校生たちの姿に観客も大いに沸いていた。
- フリーペーパー

気になるお口の健康について、歯科医の先生方が分かりやすく解説します- 特集企画

酒井家庄内入部400年を記念し、徳川家康の重臣として活躍した酒井家初代・忠次公の逸話を交え事績をたどる。
酒井家庄内入部400年を記念し、庄内藩中興の祖と称された酒井家9代・忠徳公の業績と生涯をたどる。
江戸幕府が3大名に命じた転封令。幕命撤回に至る、庄内全域で巻き起こった阻止運動をたどる。
酒井家3代で初代藩主として、庄内と酒井家400年の基盤を整えた忠勝公の事績をたどる。
幕末~明治・大正の激動期の庄内藩と明治維新後も鶴岡に住み続けた酒井家の事績をたどる。
酒井家が藩主として庄内に入部し400年を迎えます。東北公益文科大学の門松秀樹さんがその歴史を紹介します。
教育現場に身を置く筆者による提言の続編です。
子どもたちを取り巻く環境は日々変化しています。長らく教育現場に身を置く筆者が教育をテーマに提言しています。
鶴岡市櫛引地域出身の大相撲の元横綱・柏戸の土俵人生に迫ります。本人の歩み、努力を温かく見守った家族・親族や関係者の視点も多く交えて振り返ります。
藤沢周平作品の魅力を研究者などの視点から紹介しています
世界あるいは全国で活躍し、各分野で礎を築いた庄内出身の先人・先覚たちを紹介しています
旬の食べ物を使った、おいしくて簡単、栄養満点の食事のポイントを学んでいきましょう
庄内の「うまいもの」を関係者のお話などを交えながら解説しています