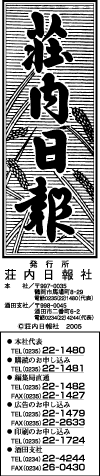- 音声ブラウザをご利用のお客様向けのリンクです。
- 本文へジャンプする
荘内日報ニュース
2025年(令和7年) 5月7日(水)付紙面より
ツイート五穀豊穣願い伝統紡ぐ ササラ響かせ花笠舞 鶴岡 民俗芸能「高寺八講」
鶴岡市羽黒町高寺の雷電神社(松平修宮司)に伝わる民俗芸能「高寺八講」(県指定無形民俗文化財)が4日、同神社の春例祭で奉納上演された。大勢の見物客が訪れ、五穀豊穣(ほうじょう)を祈る演舞に見入った。
高寺八講は鎌倉時代の古典芸能の流れをくむ貴重な古典芸能として、1976(昭和51)年に県の文化財に指定された。「八講」の名称は、法華経の講義を意味する「法華八講」に由来するといった説や、「演目がかつて八番あった」など諸説ある。明治時代半ばまでは現在より多くの演目があったというが、今は4演目を伝承している。
子どもから大人までの演者らが地区内を練り歩き、神社拝殿で祈祷(きとう)を受けた後、境内の八講楽殿に上がり、勇壮な「薙刀(なぎなた)舞」や全国でも一部でしか舞われていない貴重な「大小舞」が披露された。メインの「花笠舞」は、色鮮やかな花を差した四角い花笠をかぶり、ササラや扇を手にした6人の舞い手が独特の所作で豊作を願う田楽舞を奉納した。
「ジャッ、ジャッ」とササラの音が響く中、境内を訪れた地元住民らが舞台を見つめ、大勢のアマチュアカメラマンが盛んにシャッターを切っていた。最後に子どもたちによる稚児舞も行われた。
隣接する下馬渡地区から3歳の息子ら家族で訪れた小林亮大さん(38)は「近所の子どもが稚児舞に出るので初めて見に来た。華やかな舞を高寺地区でずっと守り伝えてきたことに驚いた。息子もいずれは稚児舞を舞うことになると思う」と話していた。
- フリーペーパー

気になるお口の健康について、歯科医の先生方が分かりやすく解説します- 特集企画

酒井家庄内入部400年を記念し、徳川家康の重臣として活躍した酒井家初代・忠次公の逸話を交え事績をたどる。
酒井家庄内入部400年を記念し、庄内藩中興の祖と称された酒井家9代・忠徳公の業績と生涯をたどる。
江戸幕府が3大名に命じた転封令。幕命撤回に至る、庄内全域で巻き起こった阻止運動をたどる。
酒井家3代で初代藩主として、庄内と酒井家400年の基盤を整えた忠勝公の事績をたどる。
幕末~明治・大正の激動期の庄内藩と明治維新後も鶴岡に住み続けた酒井家の事績をたどる。
酒井家が藩主として庄内に入部し400年を迎えます。東北公益文科大学の門松秀樹さんがその歴史を紹介します。
教育現場に身を置く筆者による提言の続編です。
子どもたちを取り巻く環境は日々変化しています。長らく教育現場に身を置く筆者が教育をテーマに提言しています。
鶴岡市櫛引地域出身の大相撲の元横綱・柏戸の土俵人生に迫ります。本人の歩み、努力を温かく見守った家族・親族や関係者の視点も多く交えて振り返ります。
藤沢周平作品の魅力を研究者などの視点から紹介しています
世界あるいは全国で活躍し、各分野で礎を築いた庄内出身の先人・先覚たちを紹介しています
旬の食べ物を使った、おいしくて簡単、栄養満点の食事のポイントを学んでいきましょう
庄内の「うまいもの」を関係者のお話などを交えながら解説しています