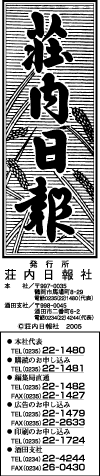- 音声ブラウザをご利用のお客様向けのリンクです。
- 本文へジャンプする
荘内日報ニュース
2025年(令和7年) 5月8日(木)付紙面より
ツイート「縁起物」に競って手を伸ばす 吹浦祭り 行列練り花笠舞披露
鳥海山大物忌神社(高橋廣晃宮司)吹浦口之宮例大祭(通称・吹浦祭り)が5日、遊佐町吹浦地区で繰り広げられた。きれいな青空の下、祭りの最後を飾る花笠舞が奉納され、終わって花笠が舞台から投げ入れられると、待ち焦がれた観客が「縁起物」を獲得しようと一斉に手を伸ばし、競って奪い合った。
鎌倉時代から続くという伝統の祭り。午後1時過ぎ、伊達奴(だてやっこ)の先導で鳥海山大物忌月山(つきやま)の両大神を祭る2基の神輿(みこし)を中心とした渡御行列が同宮を出発。晴れ着姿の子どもたちが花を手にした家族らと行列に参加する「台花持ち」、遊佐小児童の「子ども樽みこし」、地元漁師ら漁業関係者による船形の「船みこし」、県内外から多くの担ぎ手が集まる「吹浦みこし」などの行列が、露店が並ぶ同地区中心部を練り歩いた。
約2時間かけて行列が同宮に戻ると、境内の特設舞台で花笠舞を披露。青空と新緑が目に優しい林をバックに深紅の花笠が華麗、勇壮に揺れ、花笠が投げ入れられると祭りはクライマックスを迎えた。
2025年(令和7年) 5月8日(木)付紙面より
ツイート放送開始から100年 ラジオよもやま話
NHK連続テレビ小説「あんぱん」で、運動会のパン食い競争の1等商品がラジオという場面があった。台の上に“鎮座”するラジオから「前畑がんばれ」の実況放送が流れる。1936(昭和11)年の、第36回ベルリン五輪の200メートル平泳ぎで、日本初の女性金メダリストになった前畑秀子の力泳を伝えたアナウンサーの絶叫調の実況は、今も語り草になっている。
今年は25(大正14)年3月にラジオ放送が始まってから100年。ラジオは一家に1台から、トランジスタの登場で小型化するとポケットに入れて持ち運び、今や録音機能付きICラジオという優れ物も登場し小型化の進化が著しい。
■
「酒田市史年表」に「大正14年3月、金久が酒田で初めてラジオを据え付ける」の記述が。東京で放送が始まってすぐのことで、酒田の人の「新し物好き」を物語る。
酒田では商店主ら3人が放送開始の前年から受信方法を研究していて、雑音混じりの「こちらは東京放送局」という声を聞いて小躍りし、深夜放送で上海からの音楽放送も受信したという。
また、「空中は沈黙しているように見えるが、美しい音楽の音色や名士の講演は電波で送られてくる。逓信局の手続きは無料で取り扱う」との新聞広告が。当時、ラジオを聞くには仙台逓信局の「聴取無線電話施設」の許可が必要だった。
酒田では受講料2円でラジオ理論講習会を開くという、時流を捉えたちゃっかりした商売も登場。昭和初期の鶴岡では畑に高いアンテナが立てられて「ラジオが聞こえる」と人々が集まり、鶴岡公会堂でラジオを聞く会もあった。
30年12月の「鶴岡日報」。「我等の『鶴岡小唄』をラヂオとレコードに」と、ビクター会社でレコードを製作、東京放送局から電波に乗ったと伝えた。
ラジオは高価だった。安価な270円の機種から950円の高級機もあった。当時の米価は政府買入米約15円。そのせいもあってか、「鶴岡日報」に「鶴岡で認可を得た者が僅か7人」と受信者数を載せた記事が出ているが、「認可を受けずに聞いている者が56人もいる」とは、どんな方法で所有者を調べたものか。
33年の鶴岡市のラジオ加入台数は396台、会社員、医師、教員の所有が多かった。翌年8月、鶴岡公園と小学校を会場にラジオ体操が開かれた。雨で1日中止になったが、6日間で2万5775人が参加した。そして37年、待望の鶴岡放送局の設置が決まった。
■
「遊佐町史年表」の、37年7月の項に「このころ、遊佐郷にラジオ入る」とある。村費でラジオ購入したケースもあったという。戦時色が濃くなり、国際連盟脱退(33年)、二・二六事件(36年)、日中戦争(37年)など、相次ぐ不安定な世情を、いち早く知りたいという表れでもあったか。
35年7月、旧黄金村の母狩山に珍鳥・仏法僧が生息しているとの放送が話題になったこともある。
46年4月、鶴岡放送局が本格放送を開始、同5月に開局記念素人のど自慢大会が30分番組で放送された。「荘内自由新聞」は、出場者名と「ジャワのマンゴ売り」「民謡・博多夜船」などの曲目も報じている。
テレビの登場で、ラジオは存在感が薄れたかに思われたが、どんどん小型化し、インターネットの普及で、聞き逃した放送を後日聞くことができる。そして、テレビに距離を置く若者も増えている。(論説委員・粕谷昭二)
2025年(令和7年) 5月8日(木)付紙面より
ツイートもし海に沈んだらどうなるのかな? 加茂水族館で水産高生 「温暖化で沈む国」水槽で表現
もし本当に海に沈んでしまったらどうなるのか―。鶴岡市立加茂水族館(奥泉和也館長)で「温暖化で沈む国」を表現した水槽がお目見えした。
加茂水産高校海洋資源科の生徒が北極と南極の氷が解け出し「沈む国」として問題視されている太平洋に浮かぶ島「ツバル」を表した。水槽の中に家や橋の模型を配置。生き物としてタイリクバラタナゴと庄内金魚を入れた。
水槽のタイトルは「アクアタウンシップ(水中の郷)」。サンゴ礁でできているツバルは海抜が2メートルしかなく、海岸線が波で削られ「温暖化の脅威」にさらされていることを考えてもらうきっかけにした。
生徒は「ツバルの人たちのことに思いをはせながら表現した。このまま温暖化が進んだ場合、私たちの故郷もどうなってしまうのか。みんなで地球環境を守らなければならない」とメッセージを添えている。
加茂水族館では、近くの加茂水産高校とのコラボレーション企画として生徒たちが自由に展示できる2つの水槽を提供している。もう一方の水槽は「メダカの学校」。水槽の中に黒板や机を置き、本物のメダカを入れた。訪れた人たちは「生徒たちの発想とアイデアには、いつも感心させられる」と注目を集めている。
- フリーペーパー

気になるお口の健康について、歯科医の先生方が分かりやすく解説します- 特集企画

酒井家庄内入部400年を記念し、徳川家康の重臣として活躍した酒井家初代・忠次公の逸話を交え事績をたどる。
酒井家庄内入部400年を記念し、庄内藩中興の祖と称された酒井家9代・忠徳公の業績と生涯をたどる。
江戸幕府が3大名に命じた転封令。幕命撤回に至る、庄内全域で巻き起こった阻止運動をたどる。
酒井家3代で初代藩主として、庄内と酒井家400年の基盤を整えた忠勝公の事績をたどる。
幕末~明治・大正の激動期の庄内藩と明治維新後も鶴岡に住み続けた酒井家の事績をたどる。
酒井家が藩主として庄内に入部し400年を迎えます。東北公益文科大学の門松秀樹さんがその歴史を紹介します。
教育現場に身を置く筆者による提言の続編です。
子どもたちを取り巻く環境は日々変化しています。長らく教育現場に身を置く筆者が教育をテーマに提言しています。
鶴岡市櫛引地域出身の大相撲の元横綱・柏戸の土俵人生に迫ります。本人の歩み、努力を温かく見守った家族・親族や関係者の視点も多く交えて振り返ります。
藤沢周平作品の魅力を研究者などの視点から紹介しています
世界あるいは全国で活躍し、各分野で礎を築いた庄内出身の先人・先覚たちを紹介しています
旬の食べ物を使った、おいしくて簡単、栄養満点の食事のポイントを学んでいきましょう
庄内の「うまいもの」を関係者のお話などを交えながら解説しています