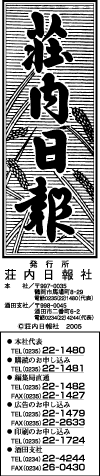- 音声ブラウザをご利用のお客様向けのリンクです。
- 本文へジャンプする
荘内日報ニュース
2025年(令和7年) 05月17日(土)付紙面より
ツイートNZへ語学演習や企業研修 鶴岡高専とワンガヌイの2者学術交流協定
鶴岡市の鶴岡工業高等専門学校(太田道也校長)は15日、ニュージーランドのワンガヌイ地区評議会、同地区にキャンパスを構える高等学術機関ユニバーサルカレッジオブラーニング(UCOL)の2者と学術交流に関する協定を締結した。今回の締結により、鶴岡高専の学生が現地を訪れて語学演習や情報分野の共同研究、現地企業でのインターンシップなどに挑戦できることになった。
鶴岡高専は適応力が高く国際社会で活躍できる技術者育成のため、年間を通して学生の海外派遣プログラムを実施するなど、学校全体のグローバル化に取り組んでいる。同校はこの一環として、英語圏で治安が良く自然豊かなニュージーランドとの交流促進を計画。昨年10月にワンガヌイ訪問団が来日した際、ニュージーランド大使館で開催された懇談会で鶴岡高専側から訪問団へ学術交流について相談を持ち掛け、同12月や今年3月には現地の企業や研究現場を訪れて連携の具体的な内容を詰めた。
協定の主な内容は「学術交流により日本とニュージーランド間の相互理解を深め、相互の関心分野における学術活動の発展に寄与する」ことを目的に掲げた上で、▽教職員・学生の交流促進▽科学技術に対する共同研究▽会議、シンポジウム、講義の開催、印刷物やその他の学術的・教育的情報交換―の3点を基に、3者が共同プログラムに取り組むといったもの。協定の有効期間は5年で、いずれかの機関が変更や廃止を提案しない限り、5年ごと自動的に延長される。
この日、鶴岡高専で締結式が行われ、ワンガヌイ地区評議会主席戦略役員のサラ・オヘイガンさんとUCOLの学術ポートフォリオ(教育評価)責任者のジャン・マクギボンさんなど5人が来校。オヘイガンさんとマクギボンさん、太田校長の3人が覚書に署名した。
その後、太田校長が「皆さんと交流を深めることに期待している。次に訪れた時はゆっくり過ごし、鶴岡の雰囲気を味わってもらいたい」、オヘイガンさんが「英語学習と実社会でのインターンシップを組み合わせたプログラムを、ワンガヌイで展開する可能性に大きな期待を寄せている」、マクギボンさんが「鶴岡高専の学生の皆さんをワンガヌイにお迎えできることを心から楽しみにしている」とそれぞれあいさつした。
※ ※
ワンガヌイ地区のワンガヌイ市は、ニュージーランド最大かつ最も歴史の古い都市の一つで、人口は約4万5000人。ユネスコのデザイン都市に認定されている。2014年に設立されたワンガヌイ地区評議会は、産業や海外との交流など各種方針について市へ提案する経済発展機関。また、UCOLは公立のポリテクニック(実学・職業教育を中心にした高等教育機関)で、ワンガヌイ地区の企業とつながりが深い。
2025年(令和7年) 05月17日(土)付紙面より
ツイート白ツツジ咲き誇る 鶴岡 釈迦堂庭園 今週末から見頃
鶴岡市泉町の旧風間家別邸「無量光苑釈迦堂」(国登録有形文化財)の庭園で白ツツジが間もなく見頃を迎える。例年通り5月初めの連休中に咲き始めたものの、その後は寒い日が続いた影響か15日は全体で5分咲きといったところ。今週末から来週頭にかけて見頃を迎える見込みだ。
釈迦堂の庭園は100年ほど前に風間家7代目の幸右衛門が造園し、現在は公益財団法人の克念社が管理している。
約2700平方メートルの土地にツツジや松、桜、ツバキ、ハギ、モミジなどの庭木を配置し、四季折々の景観を楽しめる市街地のスポット。ツツジの名所としても知られ、白と赤合わせて20株余りが植えられており、例年5月中旬に白が見頃を迎える。
15日は日中に25度前後まで気温が上昇。庭園のツツジは株によって7~8分咲きだが、つぼみも多く見られた。克念社の70代女性職員は「白ツツジが咲きそろうと圧巻の景色。縁側に座って眺めたり、ティーハウスでゆっくりしながら観賞したりと、毎年多くの市民や観光客が穏やかな時間を楽しんでいる」と話していた。
白ツツジは今月25日ごろまで、赤ツツジは今月末まで楽しめるという。丙申堂と釈迦堂の入館料は共通券500円。
2025年(令和7年) 05月17日(土)付紙面より
ツイート庄内は3月から5月に大火が多い
何の気なしに歴史年表を見ていて、庄内では3月から5月にかけ、大火の多さに気付いた。酒田市では2000戸以上焼失した大火が3度もある。海に近く「西風にあおられた」という気象条件が大火につながると言われるが、実は「東風で火勢が広がった」大火も多い。
火災は冬に多いとのイメージが強い。しかし、春の全国火災予防運動が3月1日から7日までというのは、春先は火事が多い事での注意喚起。3~5月は火災が発生しやすいのは、気象的に春は乾燥が続き、1年の中でも風が強い時期であるからのようだ。春先に野火が多いのにも、そうした背景がある。年表から主に3月から5月にかけて発生した大火を拾ってみた。
◇ ◇
酒田で最も多く家屋が焼失した火事は▽宝暦元(1751)年3月、荒瀬町(現新井田町など)から出火して住家2450戸、土蔵170棟を焼き、焼死者は80人。米・麦10万2667俵も焼いた▽明和9(1772)年4月、片町(現上本町など)から出火して住家2355戸、土蔵124棟▽享保11(1726)年5月、上片町(現同)から出火して住家2077戸を焼いたのが、一度に2000戸以上焼失した大火。
酒田の大火の記録をたどれば、宝暦8(1758)年7月、伝馬町(現中町三丁目など)から出た火事で1479戸を焼くなど、500戸以上焼失の火災が11件ある。東風、いわゆる「ダシ風」によって火勢が拡大した火事が多い。このため、宝暦年間の火災を教訓に、町の中央を南北に貫く幅約20メートルの道路「広小路」を造って柳を植えて防火帯にした。現在の「柳小路」である。昭和51(1976)年10月の酒田大火の後に、南北に貫く「大通り」が設けられた。
鶴岡市では明治13(1880)年3月、十日町から出火して住家470戸と8寺社▽同16(1883)年5月、下肴町から出火して300戸▽昭和26(1951)年4月、あつみ温泉の大火で旅館や住宅249戸などを焼失している。明治8(1875)年4月、旧朝日村大網の大日坊で即身仏2体が焼ける火災もあった。
◇ ◇
酒田市では明治以降、焼失被害が2000戸を超える火災はない。「自らは火を出さない」戒めを徹底したため。離島の飛島も火事が多く、男が漁に出た後を守るため明治43(1910)年、全国初の女性消防隊が誕生した。それでも火事があれば、火元が家を再建する時、母屋や物置の規模を小さくするペナルティーを課した。
酒田では明治6(1873)年以前の217年間に発生した100戸以上の火事は36回、実に6年に1度の割で起きている。寛政10(1798)年には一年の間に622戸、593戸、671戸など4件の大火で2075戸を焼いた火災も春に集中している。年表などから主な大火を拾ってみた。「火の用心」の時期である。
- フリーペーパー

気になるお口の健康について、歯科医の先生方が分かりやすく解説します- 特集企画

酒井家庄内入部400年を記念し、徳川家康の重臣として活躍した酒井家初代・忠次公の逸話を交え事績をたどる。
酒井家庄内入部400年を記念し、庄内藩中興の祖と称された酒井家9代・忠徳公の業績と生涯をたどる。
江戸幕府が3大名に命じた転封令。幕命撤回に至る、庄内全域で巻き起こった阻止運動をたどる。
酒井家3代で初代藩主として、庄内と酒井家400年の基盤を整えた忠勝公の事績をたどる。
幕末~明治・大正の激動期の庄内藩と明治維新後も鶴岡に住み続けた酒井家の事績をたどる。
酒井家が藩主として庄内に入部し400年を迎えます。東北公益文科大学の門松秀樹さんがその歴史を紹介します。
教育現場に身を置く筆者による提言の続編です。
子どもたちを取り巻く環境は日々変化しています。長らく教育現場に身を置く筆者が教育をテーマに提言しています。
鶴岡市櫛引地域出身の大相撲の元横綱・柏戸の土俵人生に迫ります。本人の歩み、努力を温かく見守った家族・親族や関係者の視点も多く交えて振り返ります。
藤沢周平作品の魅力を研究者などの視点から紹介しています
世界あるいは全国で活躍し、各分野で礎を築いた庄内出身の先人・先覚たちを紹介しています
旬の食べ物を使った、おいしくて簡単、栄養満点の食事のポイントを学んでいきましょう
庄内の「うまいもの」を関係者のお話などを交えながら解説しています