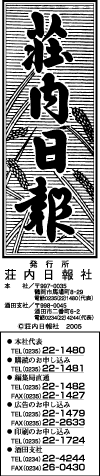- 音声ブラウザをご利用のお客様向けのリンクです。
- 本文へジャンプする
荘内日報ニュース
2023年(令和5年) 12月5日(火)付紙面より
ツイート地元食材と地域との関連考察 講演や料理人・生産者事例発表 ガストロノミーシンポジウム 鶴岡
食文化創造都市・鶴岡の“食”を通してサステナビリティ(持続可能性)とより良い食環境の循環について考える「ガストロノミーシンポジウム~『食』で地域をもっと豊かにするサステナブルな革命~」が3日、鶴岡市先端研究産業支援センターで開かれた。基調講演や市内の料理人、生産者の事例発表が行われ、地元食材と持続可能な地域の在り方の関連性などについて参加者が理解を深めた。
鶴岡食文化創造都市推進協議会(会長・皆川治鶴岡市長)主催。鶴岡市を中心に料理人や一般市民など40人余りが出席した。第1部の基調講演は、日本ジビエ振興協会代表理事で長野県のフランス料理店「オーベルジュ・エスポワール」オーナシェフの藤木徳彦さんが「人を動かすジビエの魅力」と題し、長野県で出合った鹿肉とジビエにまつわる法整備の経緯などについて語った。
この中で藤木さんは「食用として捕獲した野生鳥獣またはそれらを使った料理であるジビエは、ほんの10年ほど前まで日本の法律では食材として扱われることがなかった。長野県でジビエ勉強会を開催し、さまざまな人とのつながりができてジビエのルール作りに奔走した結果、2014年11月にようやく厚生労働省が衛生管理に関する指針を策定した」と述べた。
第2部では湯野浜温泉うしお荘の延味克士さん、ワッツワッツファームの佐藤公一さん、イタリア料理店「本町バルハレトケ」シェフの佐藤昌志さん、三井農場・ととこの三井朗さんの4人がそれぞれ事例発表。このうち延味さんは、うしお荘で提供している嚥下(えんげ)食について「宿泊する方から柔らか食、刻み食の要望が少しずつ増える中、嚥下食を考える研究会との出会いがきっかけとなった」と振り返った。
また、「一般的な嚥下食は安全を最優先し、必要な栄養を効率的に摂取する。自分が提供したかったのは、温泉宿や料理店で特別な日(晴れの日)に見た目も味も楽しめるものだった」と述べ、鶴岡産ササニシキと地魚の握りずしや庄内牛のステーキなど、さまざまな“晴れの日鶴岡食材を使った嚥下食”を紹介した。
このほか第3部ではパネルディスカッションも行われ、持続可能な地域と食について意見を交わした。