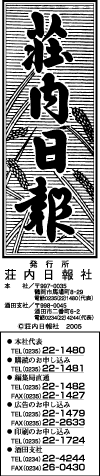- 音声ブラウザをご利用のお客様向けのリンクです。
- 本文へジャンプする
荘内日報ニュース
2023年(令和5年) 8月23日(水)付紙面より
ツイート全国・海外から56人 研究成果・計画披露 高校生バイオサミットin鶴岡 庄内の高校生も決勝発表
「第13回高校生バイオサミットin鶴岡」の決勝が21、22の両日、鶴岡市先端研究産業支援センター・レクチャーホールで行われた。全国各地と海外から56人の高校・高専生が参加し、研究の成果と計画の2つの部門で口頭発表。地元庄内地域の高校生も決勝の研究作品に選ばれ、それぞれが取り組みを堂々と発表した。
慶應義塾大先端生命科学研究所と県、鶴岡市が実行委員会をつくり、2011年から毎年、夏休みに開催している。今回は書類審査を経て、24都道府県とカナダから応募された95点(62校175人)が1回戦に進んだ。今月4日にオンラインによるライブプレゼンテーションがあり、成果発表部門20点、計画発表部門13点が決勝発表に選ばれた。
21日の開会式で、慶應先端研の荒川和晴所長があいさつし、「サイエンスの楽しみは議論することにもある。この機会に全国の仲間や研究者とさまざまな意見を交換して横のつながりをつくり、皆さんにとってこれからの糧になる大会にしてほしい」と激励した。初日は成果発表部門の決勝が行われ、高温によるカブトムシの羽化の時期のずれや、鶏卵の殻の成分特性を活用したPM2・5吸着剤開発の研究、シロアリの誘引物質の研究などを個人やグループで発表。先輩たちの研究を引き継いで年数を重ねて研究内容を高度化したり、これまで明らかになっていなかった物質の特定に至る研究成果もあり、質疑応答で審査員を務めた慶應先端研や鶴岡高専、研究機関の研究者らから「興味深く素晴らしい研究だ」「こちらが勉強になる」といった評価の声が相次いだ。
ダニが雄を雌と勘違いする「性誤認」の研究を発表した鶴岡北高3年の工藤真由美さん(17)は「ネコの耳の疾患を研究する中でダニに興味を持った。決勝発表は初めてでとっても緊張した。他の発表や審査員との質疑応答はとても刺激になる。全国の仲間と積極的に交流したい」と話した。
22日は計画部門発表の決勝が行われ、酒田東高1年の後藤心さんが「ファブリー病に関する新規治療法確立の検討」、同校2年の菅原光貴さんが「微生物の力でポリ乳酸から電気を作る」のテーマで取り組みを発表。荒川所長の講演とラボツアー、慶應大の学生・大学院生のプレゼンテーション、参加者による意見交換会なども行われた。最終日の23日に両部門の審査結果が発表され、表彰式が行われる。