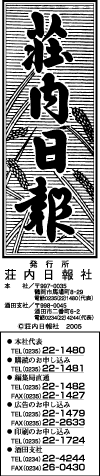- 音声ブラウザをご利用のお客様向けのリンクです。
- 本文へジャンプする
荘内日報ニュース
2024年(令和6年) 5月1日(水)付紙面より
ツイート豊作願う湯立神楽 酒田 飛鳥神社「湯の花祭」
酒田市の飛鳥神社で27日、五穀豊穣(ほうじょう)や国の安寧を願う祈年祭「湯の花祭」が行われ、「湯立(ゆたて)神楽」(市指定無形民俗文化財)を奉納上演したほか、鉄鍋にお湯を沸かし今年の吉凶を占った。
同神社は約1200年前、大和国(奈良県)の飛鳥坐神社を分祀したとされている。湯立神楽は伊勢神楽系統に属する修験神楽で、社記には江戸時代初期の元和8(1622)年には行われていたという記録が残り、それ以前の中世から連綿と受け継がれてきたとみられている。
この日は、長さ約5メートルの棒に「湯釜(ゆがま)」と呼ばれる鉄鍋を、うるう年のため例年に比べて1個多い13個ぶら下げた斎場を社殿前に設営。午後1時半から社殿内で神事を行った後、同2時半過ぎから斎場脇の特設舞台で神楽が始まった。地元の女子生徒による巫女舞(みこまい)、男子児童たちによる「露拂招(つゆはらいまねぎ)」などに続き、神官たちが神々の国土経営など表現した「神(かむ)」といった舞を次々に披露、詰め掛けたアマチュア写真家らが盛んにシャッターを切っていた。
引き続き「釜若勢」と呼ばれる氏子が水を張った湯釜の下から豆がらで火をたき、湯を沸かした。神官がクマザサで湯をかき混ぜるような仕草をした後、社殿で神々しく舞った。地域住民たちは豊作を願いながら静かに見入っていた。
Loading news. please wait...