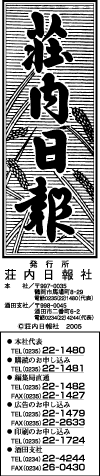- 音声ブラウザをご利用のお客様向けのリンクです。
- 本文へジャンプする
荘内日報ニュース
2024年(令和6年) 4月27日(土)付紙面より
ツイート「萩名工選抜展」人間国宝から中堅作家まで 伝統継ぐ逸品や革新的作品並ぶ
山口県萩市の「萩焼」をつくる名工たちの逸品を集めた「萩名工選抜展~人間国宝から中堅作家まで~」が鶴岡市末広町のマリカ東館の庄内産業振興センターで開かれている。同じ萩焼ながら釉薬の使い方、焼成の方法で色合いが変わり、伝統を継承した作品や革新的な品も並び来場者の目を楽しませている。
400年以上の歴史を持つ萩焼は土の柔らかな風合いが特徴で、浸透性や保水性に優れる。焼成による土と釉薬の伸縮率差で生まれる表面の貫入(細かなひび)から水分が浸透し、使い込むほど色合いが変化し、素朴ながら独特の深い味わいとなる。近年は釉薬や焼成技術の進歩に加えデザイン性も高まっており、茶道具のほか日常的な食器なども作られている。
展示会は萩市の公信堂熊谷美術(熊谷隆代表)の主催。著名な作家の作品を多くの人に鑑賞してもらい、美術工芸品を身近に感じてもらうため全国各地で萩焼の展示会を開催している。
今回は茶道具や花器を中心に100点余りを展示。会期中の入れ替えもあり累計で120点以上の展示数になるという。人間国宝の11代三輪休雪(壽雪)氏(1910~2012年)をはじめ、革新的な造形に挑む12、13代休雪氏、「萩伊羅保」というジャンルを確立した野坂康起氏、康起氏の息子で黒彩の作品を数多く手掛ける和左氏、青萩を完成させた納富晋氏など約20人の作品が並んだ。
このうち11代休雪氏の作品「白萩割高台茶碗」や「白萩耳付水指」は、厚く掛かった白の釉薬が目を引く。荒い土灰を用いた手法で「鬼萩」と呼ばれ、ごつごつとしたつくりの中に野性的な美を感じる。対照的に11代休雪氏の孫に当たる三輪華子さんの作品「萩 日の出」は洗練されたフォルムと早朝の空のような色合いで「姫萩」と呼ばれる。
このほか野坂和左さんの作品は黒彩で仕上げた椀やぐい呑みなどで、萩焼の伝統を残しながらも独特のデザインを追求した革新的な作風がそろっている。
展示は29日(月)まで。時間は午前10時から午後5時(最終日のみ午後4時まで)。入場無料。
期間中、加賀蒔絵の名匠・吉田華正さんの作品展も同時開催している。