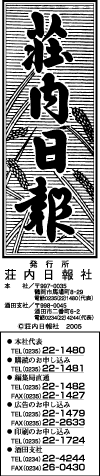- 音声ブラウザをご利用のお客様向けのリンクです。
- 本文へジャンプする
荘内日報ニュース
2025年(令和7年) 2月16日(日)付紙面より
ツイート「つるおかコンポスト」生産施設建設着工 現行の3倍 ほぼ全量活用 市浄化センター敷地内に整備 27年度4月の稼働開始目指す
下水道処理で発生する汚泥を資源にした肥料「つるおかコンポスト」を生産する新たな施設整備の安全祈願祭が14日、建設場所となる鶴岡市宝田三丁目の市浄化センターで行われた。来月から工事を本格化させ、2027年4月の稼働開始を見込んでいる。
同市が、稼働から40年ほど経過する同センター近くの現施設を更新するもので、センター敷地内に移転整備する形となる。現施設は老朽化により稼働率を制限し生産量を減らしており、汚泥発生量の3割程度の活用にとどまっている。現在の年間コンポスト生産量530トンを、新施設では発生量のほぼ全量活用によって現行の3倍となる1620トンの生産を目指す。
新施設は鉄骨造り平屋建て、広さ3500平方メートル。パドル式攪拌(かくはん)装置で現行と同じく脱水汚泥に水稲のもみ殻約3割を交ぜて発酵させるコンポスト化設備と、出荷に向けた「フレコン詰め」「袋詰め」する製品化設備を備える。36億8000万円の整備事業費のうち約半分は国の交付金で賄う。整備は水ingエンジニアリング・石庄建設・山田工務店・アベ電工特定建設工事共同企業体が担う。
安全祈願祭には市や工事関係者ら約40人が出席。神事を行い、皆川治市長らが鍬(くわ)入れした。発注者として皆川市長は「(下水汚泥ともみ殻によるコンポスト生産は)鶴岡市が全国のフロントランナーだと自負している。海外に依存する肥料や化学肥料をコンポストに置き換えられるよう、地元農家の期待に応えていきたい」とあいさつした。
市は、コンポスト増産に伴う利用促進に向け、関係者による検討組織を立ち上げた。施肥が容易になるようコンポスト製品のペレット化の検討を進めるほか、国が国内資源の利用拡大に向け新たに定めた規格「菌体りん酸肥料」の登録を目指す。登録されると、他の肥料との混合も認められることから、地域内の農家に限らず肥料メーカーへの原料としての供給も可能になるという。
- フリーペーパー

気になるお口の健康について、歯科医の先生方が分かりやすく解説します- 特集企画

酒井家庄内入部400年を記念し、徳川家康の重臣として活躍した酒井家初代・忠次公の逸話を交え事績をたどる。
酒井家庄内入部400年を記念し、庄内藩中興の祖と称された酒井家9代・忠徳公の業績と生涯をたどる。
江戸幕府が3大名に命じた転封令。幕命撤回に至る、庄内全域で巻き起こった阻止運動をたどる。
酒井家3代で初代藩主として、庄内と酒井家400年の基盤を整えた忠勝公の事績をたどる。
幕末~明治・大正の激動期の庄内藩と明治維新後も鶴岡に住み続けた酒井家の事績をたどる。
酒井家が藩主として庄内に入部し400年を迎えます。東北公益文科大学の門松秀樹さんがその歴史を紹介します。
教育現場に身を置く筆者による提言の続編です。
子どもたちを取り巻く環境は日々変化しています。長らく教育現場に身を置く筆者が教育をテーマに提言しています。
鶴岡市櫛引地域出身の大相撲の元横綱・柏戸の土俵人生に迫ります。本人の歩み、努力を温かく見守った家族・親族や関係者の視点も多く交えて振り返ります。
藤沢周平作品の魅力を研究者などの視点から紹介しています
世界あるいは全国で活躍し、各分野で礎を築いた庄内出身の先人・先覚たちを紹介しています
旬の食べ物を使った、おいしくて簡単、栄養満点の食事のポイントを学んでいきましょう
庄内の「うまいもの」を関係者のお話などを交えながら解説しています