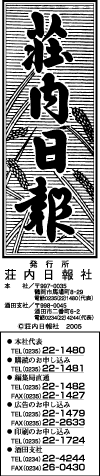- 音声ブラウザをご利用のお客様向けのリンクです。
- 本文へジャンプする
荘内日報ニュース
2025年(令和7年) 4月23日(水)付紙面より
ツイート本を開いて知らない事を学ぼう
23日から「第67回こどもの読書週間」が始まる。2025年の標語は「あいことばは ヒ・ラ・ケ・ホ・ン!」―。そう、本を開いてページをめくれば、そこには未知の世界が広がっている。書いてあることを知り、そこから想像力を広げる。全国では書店ゼロの自治体が増え、そして町の本屋さんも減っている。本は知識の玉手箱で、読めば世界が広がる。
「こどもの読書週間」は1959年に始まり、2000年の「子ども読書年」から4月23日から約3週間実施されるようになった。政府も「子ども読書活動推進法」によって後押ししている。4月23日は、「世界本の日」とも呼ばれ、欧州では親しい人に本を贈る記念日とする国もあるという。
◇ ◇
こどもの読書週間は「小さいときから本を読む楽しさを知っていることは、子どもが大きくなるために大切なこと」との趣旨で始まった。読書離れが進んでいると言われる。ただ、小中高校生が全く本を読まなくなったわけではない。スマートフォンなどで活字に触れてはいるものの、紙の書籍に触れなくなっている傾向を否定することはできない。
今年の「こどもの読書週間」の標語にあるように、本を開く。そこには知らない事柄がたくさん詰まっている。本を読んで知らなかった事を知る。物事を知れば知るほど、「なぜ、どうして」と、もっと知りたい事、疑問が出てきて、別の本を読んで調べるという展開につながる。論語に「自分が知らないという事を認めることが真に『知る』ことだ」という趣旨の教えがある。物事を知ることで自分が「知的」になり、成長につながる。
「読む」ことは、全ての学習の基本。読んで文章が問い掛けている意味を理解しなければ、テストの問題は解けない。読解力を高めるためにはどれぐらい夢中になって読むかが大切といわれる。大人が読ませたい、読んでほしいと思う本を無理に読ませるより、子どもが興味を持っている本を読むことがいいという。
◇ ◇
かつて、電車通学で本を広げていた高校生の手にはスマホが握られているようになった。その姿だけで読書離れと結び付けることはできない。ネットで買える電子書籍も普及しているからだ。ただ、町の本屋に立ち寄り、偶然出会う本もある。書店の減少は、そうした機会も薄れることになる。
スマホなどは便利な存在だ。しかしネットにはうそか本当かが分からない情報もある。その中から「正確」を選択する力、物事を思考して読み解く力を養うためにも本に触れたい。漫画やコミック雑誌は人気があり、書店にはシリーズものが並んでいる。小説離れに歯止めをかけるため、馴染みの深いアニメや漫画を小説化した本もある。それでもいい、とにかく子どもが本を手にする機会が増えることを願いたい。
- フリーペーパー

気になるお口の健康について、歯科医の先生方が分かりやすく解説します- 特集企画

酒井家庄内入部400年を記念し、徳川家康の重臣として活躍した酒井家初代・忠次公の逸話を交え事績をたどる。
酒井家庄内入部400年を記念し、庄内藩中興の祖と称された酒井家9代・忠徳公の業績と生涯をたどる。
江戸幕府が3大名に命じた転封令。幕命撤回に至る、庄内全域で巻き起こった阻止運動をたどる。
酒井家3代で初代藩主として、庄内と酒井家400年の基盤を整えた忠勝公の事績をたどる。
幕末~明治・大正の激動期の庄内藩と明治維新後も鶴岡に住み続けた酒井家の事績をたどる。
酒井家が藩主として庄内に入部し400年を迎えます。東北公益文科大学の門松秀樹さんがその歴史を紹介します。
教育現場に身を置く筆者による提言の続編です。
子どもたちを取り巻く環境は日々変化しています。長らく教育現場に身を置く筆者が教育をテーマに提言しています。
鶴岡市櫛引地域出身の大相撲の元横綱・柏戸の土俵人生に迫ります。本人の歩み、努力を温かく見守った家族・親族や関係者の視点も多く交えて振り返ります。
藤沢周平作品の魅力を研究者などの視点から紹介しています
世界あるいは全国で活躍し、各分野で礎を築いた庄内出身の先人・先覚たちを紹介しています
旬の食べ物を使った、おいしくて簡単、栄養満点の食事のポイントを学んでいきましょう
庄内の「うまいもの」を関係者のお話などを交えながら解説しています