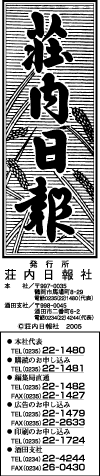- 音声ブラウザをご利用のお客様向けのリンクです。
- 本文へジャンプする
荘内日報ニュース
2025年(令和7年) 4月26日(土)付紙面より
ツイート海洋少年団でたくましく育て
「少子化だけではなく、子どもたちの生活が多様化し、日常が忙しくなった影響だろうか」―。全国で最も長い歴史を持つ「酒田海洋少年団」が2025年、団設立以来初めて年度当初の新入団員がいなかった。冒頭は長年団活動を見守ってきた鈴木兵一団長の言葉。伝統が先細りしていくことへのやるせない気持ちが表れているようだ。
童謡、文部省唱歌の『われは海の子』。2番に〈…波を子守歌と聞き…寄せて来る海の気と風に当たって、わらべとなりにけり…〉というような意味合いの歌詞がある。浜辺と松原に近い環境、つまりは潮風に当たってたくましく成長した様子を歌ったものという。
◇ ◇
酒田海洋少年団は1951年、日本海洋少年団連盟の発足と同時に設立。それ以来活動を休止しないで存続しているのは全国で酒田、横浜、神戸の3少年団だけ。設立初期には約400人もの団員がいた。酒田には北前船の往来で港町文化がもたらされた。港町酒田のにぎわいは、子どもたちを海への夢に誘った。86年には日本海洋少年団全国大会も酒田で開かれた。
海に関する知識を学ぶことは、四方を海に囲まれた日本ではごく自然の流れ。港がある酒田の環境は、子どもたちの夢を海洋少年団へと引き付けた。現在の活動は原則として毎週日曜日、市総合文化センターを拠点に手旗訓練、ロープ結索、カヌー訓練など、海に親しむことのできる活動をしている。
海に学ぶことでは、日本財団の「海と日本プロジェクトin山形」の取り組みがある。県内の小学高学年が対象の「海洋塾」で、庄内浜の漁業や食文化を学ぶ。加茂水産高校の漁業実習船「鳥海丸」で体験航海、海中を観察して庄内浜の生き物を知る。併せて海のごみなどの自然環境を学び、未来の暮らしに生かす活動をしている。酒田海洋少年団では「人を助けて親切にする、礼儀を正しく守る」―などの、人としての生き方のマナーをも学んでいる。
◇ ◇
全国的に海洋少年団の数が減っているという。子どもの生活が多様化し、クラブ活動や部活動で時間的に忙しくなったということは否めないようだ。もちろん勉強も。ただ、家に居ながらにして楽しむゲームのとりこになってはいないだろうか。「インドア派」から、時には「アウトドア派」になることも大事だ。
子どものころから海に関する知識を学ぶ。そのような場の海洋少年団でさまざまな経験を積めば、人づくりにつながる活動になる。港がある酒田市ならではの活動だ。年度当初の新入団者はいなかったが、前年からの進級者は活動している。希望者はいつでも入団できる。ぜひ鈴木団長=電090(3367)2638=に問い合わせてもらいたい。酒田の「人づくり文化」を守るためにも。
- フリーペーパー

気になるお口の健康について、歯科医の先生方が分かりやすく解説します- 特集企画

酒井家庄内入部400年を記念し、徳川家康の重臣として活躍した酒井家初代・忠次公の逸話を交え事績をたどる。
酒井家庄内入部400年を記念し、庄内藩中興の祖と称された酒井家9代・忠徳公の業績と生涯をたどる。
江戸幕府が3大名に命じた転封令。幕命撤回に至る、庄内全域で巻き起こった阻止運動をたどる。
酒井家3代で初代藩主として、庄内と酒井家400年の基盤を整えた忠勝公の事績をたどる。
幕末~明治・大正の激動期の庄内藩と明治維新後も鶴岡に住み続けた酒井家の事績をたどる。
酒井家が藩主として庄内に入部し400年を迎えます。東北公益文科大学の門松秀樹さんがその歴史を紹介します。
教育現場に身を置く筆者による提言の続編です。
子どもたちを取り巻く環境は日々変化しています。長らく教育現場に身を置く筆者が教育をテーマに提言しています。
鶴岡市櫛引地域出身の大相撲の元横綱・柏戸の土俵人生に迫ります。本人の歩み、努力を温かく見守った家族・親族や関係者の視点も多く交えて振り返ります。
藤沢周平作品の魅力を研究者などの視点から紹介しています
世界あるいは全国で活躍し、各分野で礎を築いた庄内出身の先人・先覚たちを紹介しています
旬の食べ物を使った、おいしくて簡単、栄養満点の食事のポイントを学んでいきましょう
庄内の「うまいもの」を関係者のお話などを交えながら解説しています