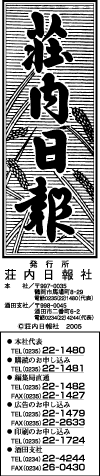- 音声ブラウザをご利用のお客様向けのリンクです。
- 本文へジャンプする
荘内日報ニュース
2025年(令和7年) 4月30日(水)付紙面より
ツイート県人口が100万人を割り込むか
県人口がついに100万人を割り、5月から90万人台の時代に入る見通しを県が発表した。県人口は1920(大正9)年の96万8925人から、25(同14)年の国勢調査で102万7297人と初めて100万人を超えた。90万人台になれば、大正の国調以来100年にして大台を割ることになる。日本全体が人口減少期に入っている。県人口の減少も避けられないとしても、残念でならない。
県は、毎月1日時点での人口を発表しており、3月1日時点の人口は100万4507人。これまで毎月1000人前後減少しているが、年度末は進学や就職などによる「社会減」が増え、例年3月は全体で4000人ほど減っていることで、5月1日時点で90万人台になる見通しという。
◇ ◇
県の人口の最多は、戦後のベビーブームを反映した50(昭和25)年の135万7347人。それをピークに減少が続き、2007(平成19)年に120万人を、18(同30)年に110万人を割った。120万人から110万人を割るまで11年、100万人を割るとなれば7年間でのことになり、人口減少が加速していることを裏付ける。
人口減少の要因となっている、県のデータがある。1980年の出生数1万6871人に対し、2010年は8651人とほぼ半減。婚姻数はそれぞれ7601件、5159件で2442件も減っている。人口構成でも1920年の高齢化率(65歳以上)4・5%が、2023年は35・2%。人口ピラミッドも高齢者が大きく膨らんで逆三角形型になって14歳以下が少なく、建物に例えれば土台が弱く安定性がない。18~29歳が細くなっているのは、若者の県外流出を意味しているのでないか。
5月1日時点の人口は5月末に発表される予定だ。吉村美栄子知事は定例記者会見で、若者や女性の定着などに取り組み、打開策を探るため県民の意見を聞く場を複数回設け、定住や移住の促進だけでなく、外国人材の受け入れを進めていく考えを示している。
◇ ◇
婚姻数が減り、出生数を死亡者数が上回っている現状から推測すれば、今後も人口減少が続くものとみられる。少子化と高齢化で生産年齢人口(14~64歳)も減っていることは、県の活力を生み出すことにも影響する。
中央では経済活動を反映して大手企業が新卒初任給を大幅にアップした。しかし、地方の企業はそうした賃金体系を導入することはなかなか難しいこともある。都市と地方との格差が広がる「二極化」が進めば、進学などで首都圏に出たまま故郷に戻らない人離れが加速する。地元では、高校生や大学生が「故郷のいい所探し」をしている。政府は30年代に入るまでが少子化傾向を反転できるか否かのラストチャンスに位置付けている。実効性のある施策の具現化が求められる。
- フリーペーパー

気になるお口の健康について、歯科医の先生方が分かりやすく解説します- 特集企画

酒井家庄内入部400年を記念し、徳川家康の重臣として活躍した酒井家初代・忠次公の逸話を交え事績をたどる。
酒井家庄内入部400年を記念し、庄内藩中興の祖と称された酒井家9代・忠徳公の業績と生涯をたどる。
江戸幕府が3大名に命じた転封令。幕命撤回に至る、庄内全域で巻き起こった阻止運動をたどる。
酒井家3代で初代藩主として、庄内と酒井家400年の基盤を整えた忠勝公の事績をたどる。
幕末~明治・大正の激動期の庄内藩と明治維新後も鶴岡に住み続けた酒井家の事績をたどる。
酒井家が藩主として庄内に入部し400年を迎えます。東北公益文科大学の門松秀樹さんがその歴史を紹介します。
教育現場に身を置く筆者による提言の続編です。
子どもたちを取り巻く環境は日々変化しています。長らく教育現場に身を置く筆者が教育をテーマに提言しています。
鶴岡市櫛引地域出身の大相撲の元横綱・柏戸の土俵人生に迫ります。本人の歩み、努力を温かく見守った家族・親族や関係者の視点も多く交えて振り返ります。
藤沢周平作品の魅力を研究者などの視点から紹介しています
世界あるいは全国で活躍し、各分野で礎を築いた庄内出身の先人・先覚たちを紹介しています
旬の食べ物を使った、おいしくて簡単、栄養満点の食事のポイントを学んでいきましょう
庄内の「うまいもの」を関係者のお話などを交えながら解説しています