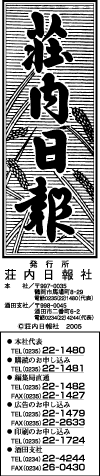- 音声ブラウザをご利用のお客様向けのリンクです。
- 本文へジャンプする
荘内日報ニュース
2025年(令和7年) 5月3日(土)付紙面より
ツイート東部中生も勇ましく 松山まつり「武者行列」
酒田市松山地域にある中山神社(白井知行宮司)の例大祭「松山まつり」が1日、同地域中心部で行われ、呼び物の「武者行列」(酒田市指定無形民俗文化財)で、武具甲冑(ぶぐかっちゅう)の武者たちが勇ましく練り歩いた。
同神社は、江戸前期の1647(正保4)年に庄内松山藩の初代藩主・酒井忠恒公が立藩した翌慶安元年に創建。その後、庄内藩祖・酒井忠次公と、徳川家康の嫡男・信康公を祭るために社殿を造営した。信康公を祭るのは、織田信長の命で同公が切腹した際、忠次公が深く関わっていた縁。
武者行列は、1757(宝暦7)年ごろから祭典の神輿(みこし)渡御を警護したのが始まりといわれ、250年以上続いている。今年は中山神社の氏子や東部中学校の生徒ら約100人が参加した。
この日は晴天で絶好の祭り日和。午後1時に神社前を出発。かみしも姿の武者を先頭に、鉄砲組や弓組、足軽組、騎乗の行列奉行、侍大将らの鎧(よろい)武者が、松山歴史公園や内町など中心部約4キロを3時間ほどかけて練り歩いた。
このうち、松山歴史公園では、松山城大手門(県指定有形文化財)をバックにした姿が特に“絵”になることから大勢の見物客が待ち受け、盛んにカメラのシャッターを切るなど歴史絵巻を楽しんでいた。
- フリーペーパー

気になるお口の健康について、歯科医の先生方が分かりやすく解説します- 特集企画

酒井家庄内入部400年を記念し、徳川家康の重臣として活躍した酒井家初代・忠次公の逸話を交え事績をたどる。
酒井家庄内入部400年を記念し、庄内藩中興の祖と称された酒井家9代・忠徳公の業績と生涯をたどる。
江戸幕府が3大名に命じた転封令。幕命撤回に至る、庄内全域で巻き起こった阻止運動をたどる。
酒井家3代で初代藩主として、庄内と酒井家400年の基盤を整えた忠勝公の事績をたどる。
幕末~明治・大正の激動期の庄内藩と明治維新後も鶴岡に住み続けた酒井家の事績をたどる。
酒井家が藩主として庄内に入部し400年を迎えます。東北公益文科大学の門松秀樹さんがその歴史を紹介します。
教育現場に身を置く筆者による提言の続編です。
子どもたちを取り巻く環境は日々変化しています。長らく教育現場に身を置く筆者が教育をテーマに提言しています。
鶴岡市櫛引地域出身の大相撲の元横綱・柏戸の土俵人生に迫ります。本人の歩み、努力を温かく見守った家族・親族や関係者の視点も多く交えて振り返ります。
藤沢周平作品の魅力を研究者などの視点から紹介しています
世界あるいは全国で活躍し、各分野で礎を築いた庄内出身の先人・先覚たちを紹介しています
旬の食べ物を使った、おいしくて簡単、栄養満点の食事のポイントを学んでいきましょう
庄内の「うまいもの」を関係者のお話などを交えながら解説しています