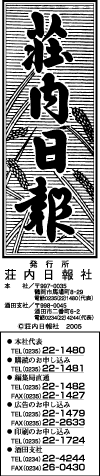- 音声ブラウザをご利用のお客様向けのリンクです。
- 本文へジャンプする
荘内日報ニュース
2025年(令和7年) 5月10日(土)付紙面より
ツイート人が減る事の歯止め策はないか
大型連休が終わった。酒田市では連休中に「二十歳を祝う成人の集い」が開かれ、首都圏から帰省した人もいて、いっときだが街は華やいだ。一方、総務省の発表で4月1日時点の外国人を含む15歳未満の子どもの数が、昨年より35万人少ない1366万人だった。44年続けての減少で、比較可能な1950年以降で初めて1400万人を割り込んだ。
厚生労働省の人口動態統計で、2024年に県内で生まれた子ども(出生数)は4999人で初めて5000人を割った。県人口も今月1日時点で100万人を割っていることが確実視されている。将来を担う子どもがどんどん減ることに、ブレーキをかける手だてはないのだろうか。
◇ ◇
県の2000年の出生数は1万828人。それから24年で出生数が半減した。人口1000人当たりの出生数も全国平均を下回っている。庄内の今年4月1日時点の人口は2市3町で24万3947人。生まれる子どもより亡くなる人が約6倍。転出者も転入者より1・8倍多い。世帯数減も県全体の251世帯のうち、庄内は107世帯を占める。
20年の年齢別人口のグラフは、右肩上がりで高齢人口が増えていて70~75歳が1万8966人。1歳児は5738人で、少子高齢化の現実をはっきり裏付けている。少子化の背景には婚姻数の減少が挙げられる。政府も児童手当の拡充、育児休業取得を支援するなどの子育て対策を講じているが、その恩恵が非正規雇用者や自営業まで及ぶかとなると疑問符が付く。
人口減少の中で、酒田光陵高生が「さがだ 運命(うんめぇ)の出会い」と銘打って、地元企業とのコラボ商品・さつまいも塩どらやきを作ったり、遊佐高生が「枝豆ポタージュ」を工夫して販売するなど、庄内の良さ探しをしている。高校生や大学生が地元農産物の良さを見直して活用、観光ガイドブックなどを作って庄内を盛り立てようとしているのは頼もしい。若者の意気込みが、人口減少のブレーキ役になってくれることを願いたい。
◇ ◇
県内の高校生の県内企業への就職率は、23年3月卒業で98・9%と高い。地元志向の高まりであろうか。一方、県外への転出を19~23歳層が多くを占めるのは、大学進学の表れとみられている。県の統計では、この年齢層の県内の平均給与は全国平均より約2万2000円下回る。
少子化は、地方の活力を将来に持続させることを厳しくする。どうしたら地方から子どもが減ることを止めることができるだろうか。政府は子育て支援策などを講じているものの、まず取り組むべきは非正規雇用をなくする構造改革に取り組むべきではないだろうか。多様な働き方に重きを置いてばかりでは、地域間格差を生じさせることにもなる。
- フリーペーパー

気になるお口の健康について、歯科医の先生方が分かりやすく解説します- 特集企画

酒井家庄内入部400年を記念し、徳川家康の重臣として活躍した酒井家初代・忠次公の逸話を交え事績をたどる。
酒井家庄内入部400年を記念し、庄内藩中興の祖と称された酒井家9代・忠徳公の業績と生涯をたどる。
江戸幕府が3大名に命じた転封令。幕命撤回に至る、庄内全域で巻き起こった阻止運動をたどる。
酒井家3代で初代藩主として、庄内と酒井家400年の基盤を整えた忠勝公の事績をたどる。
幕末~明治・大正の激動期の庄内藩と明治維新後も鶴岡に住み続けた酒井家の事績をたどる。
酒井家が藩主として庄内に入部し400年を迎えます。東北公益文科大学の門松秀樹さんがその歴史を紹介します。
教育現場に身を置く筆者による提言の続編です。
子どもたちを取り巻く環境は日々変化しています。長らく教育現場に身を置く筆者が教育をテーマに提言しています。
鶴岡市櫛引地域出身の大相撲の元横綱・柏戸の土俵人生に迫ります。本人の歩み、努力を温かく見守った家族・親族や関係者の視点も多く交えて振り返ります。
藤沢周平作品の魅力を研究者などの視点から紹介しています
世界あるいは全国で活躍し、各分野で礎を築いた庄内出身の先人・先覚たちを紹介しています
旬の食べ物を使った、おいしくて簡単、栄養満点の食事のポイントを学んでいきましょう
庄内の「うまいもの」を関係者のお話などを交えながら解説しています