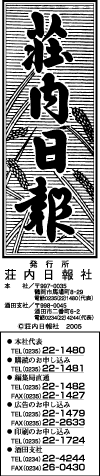- 音声ブラウザをご利用のお客様向けのリンクです。
- 本文へジャンプする
荘内日報ニュース
2025年(令和7年) 3月15日(土)付紙面より
ツイート「食の都庄内」担う若手と交流 三川
次世代を担う若手の料理人や農業者が活動紹介を行う「食の都庄内」交流会が10日、三川町のいろり火の里なの花ホールで開かれ、実践発表や試食会などが行われた。
庄内の2市3町と県庄内総合支庁で構成する「食の都庄内」ブランド戦略会議の主催。20周年を迎え、次代の「食の都庄内」を担う若手が元気に生き生きと活躍する姿を広く周知するとともに、業種を超えた同世代の親睦と交流を図ろうと開催。「食の都庄内」サポーターや食に携わる協力者ら約100人が参加した。
第1部では「食の都庄内」親善大使の奥田政行さん、土岐正富さん、古庄浩さん(メッセージ)の3人が、これまで行ってきた庄内を食の都に押し上げる取り組みを紹介するとともに次世代にエールを送った。第2部では「食の都庄内」のウェブマガジン「Cheer!!(チアー)」で取り上げた料理人と農業者3人が登壇。食のプロデュース活動を行う小野愛美さんが進行役となり、それぞれの取り組みや食への思いを聞いた。
鶴岡市の日本料理店「庄内ざっこ」料理人の齋藤翔太さん(41)は自身が代表を務める食育団体「サスティナ鶴岡」で、子どもたちが食文化を体験する中で調理や郷土食などに興味を持つようになったことなどを紹介。庄内町でブルーベリーなどの栽培と加工などを行う「はらぺこファーム」の高橋紀子さん(47)は規格外作物の加工や商品開発、1日に400人が訪れるマルシェの開催などについて発表した。酒田市のフレンチレストラン「Nico」オーナーシェフの太田舟二さん(49)は親善大使だった父の故・政宏さんとの思い出を語るとともに、フランスの二つ星レストランで修業したことで「その土地でしか味わえない料理を提供できる地方のレストランの可能性を感じた」と話した。
第3部では登壇者3人が庄内産の食材で作った▽庄内豚の味噌煮▽庄内浜の鯛のパイ包み▽月山の粉雪を使ったカンパーニュ▽ブラックベリーソース―などを試食したほか、庄内の企業や料理店の加工品などが展示された。参加者はテーブルを囲みながら、製造の工夫を聞くなどして交流していた。
2025年(令和7年) 3月15日(土)付紙面より
ツイートオウレン見頃 八森自然公園
酒田市の八森自然公園内の遊歩道に自生しているオウレンが見頃を迎え、散策客にひと足早く「春到来」を告げている。
オウレンは背丈が約10センチほどのキンポウゲ科常緑多年草で、数少ない日本特有の薬用植物。同公園内では大きく2カ所の遊歩道に広く自生している。毎年2月中旬ごろの雪解けとともに頭をもたげて咲き始め、数センチの白く小さい花が約1カ月間咲き続ける。
毎年開花を確認している八幡総合支所地域振興係の池田久浩さんによると、今年は2月の降雪影響で同月27日ごろから咲き始め、例年より少し遅い開花という。池田さんは「昨年7月に発生した豪雨災害の影響が少し心配だったが、雪解けとともに一斉に咲き始めたのを見て安心した」と。
今月11日には遊歩道周辺の一面にかわいらしい白い花が咲き誇り、小さなミツバチたちがせわしなくオウレンの蜜を集める姿が見られた。見頃は今月いっぱいまで。池田さんは「豪雨災害による同公園の目立った被害はなく、安全に自生植物を楽しめるのでぜひ訪れてもらえたら」と話した。オウレンの開花を皮切りに、カタクリやショウジョウバカマなどが咲き始めるという。
2025年(令和7年) 3月15日(土)付紙面より
ツイート絵本が秘める存在感は大きい
絵本とは「絵を中心にして簡単な文を付けた本。主に、子供向けの本をいう」と、辞典に出ている。しかし、絵本が持つ力は大きい。鶴岡市の「読書で元気なまちをつくろう市民の集い」で講演した作家の柳田邦男さんは「大人こそ絵本を読もう」と呼び掛けている。たかが絵本と軽く見てはいけないことになる。
鶴岡商工会議所青年部が今年も、鶴岡市立図書館に幼児の背丈ほどある絵本を含む7冊の絵本を寄贈した。寄贈は今回で50回目。大型絵本の寄贈は10年ほど前から始め、子どもに人気のようだ。幼い頃から本好きになれば、大人になっても本に触れる生活スタイルが続くのではないか。
◇ ◇
絵本とは別の話。鶴岡市朝日地域の旧大網小田麦俣分校を活用した「たにしの楽校」は、童謡詩人・金子みすゞの作品を展示している。先頃、同楽校をテーマにした紙芝居が作られたという。紙芝居は絵を1枚ずつめくって物語の展開を語り聞かせる。このとき、子どもたちは「次はどんな絵が、どんな物語が」と想像を巡らす。絵本もそれと同じではないだろうか。
最近は子どもの生活スタイルの変化からか、日の出や夕日を見た事のない子どもが増えていると言われる。外に出掛けることが少なくなったせいか、そうした光景を見ても感動しない子どもが増えているとの指摘もある。目まぐるしく動く動画やアニメに興味を持ち、アニメのキャラクターの話し言葉も、倍速のような早口になって、せわしなくなった。映像の流れを追いかけていては、物事を自分なりに想像することの大切さが損なわれる気がしてならない。
全国学校図書館協議会などが実施している「読書感想画中央コンクール」は、今年で36回になる。感想文と違って、本を読みながら作品が描く物語と情景を想像して絵にする。読み進むうちに自分自身が作品の中に溶け込み、作品の世界を疑似体験しているからこそ、作品を1枚の絵に凝縮して表現できるのではないだろうか。
◇ ◇
鶴岡商工会議所青年部が寄贈した大型絵本には、縦116センチ、横21センチという大判サイズもある。普段は手に持つサイズの本を見ている子どもたちにとって、自分の背丈ほどもある絵本の大きさに驚き、強い印象が心に残ることだろう。それが、本好きにつながるだろうことを信じたい。
言葉は使ったり話さないでいると、言葉の表現力が衰えると言われる。絵本には、分かりやすく優しい言葉が詰まっている。短い文章で物事をしっかり説明しているため「珠玉」の日本語でつづられていることで、辞典の説明以上の力を、絵本は秘めているのではないか。温かい心を育むためにも、寄贈された絵本だけでなく、多くの絵本に触れる機会を持ちたい。ただぼーっとして見ているだけでも、何かしら心に響くものが、絵本にはあるかもしれない。
2025年(令和7年) 3月15日(土)付紙面より
ツイート未来を描き希望胸に 思い出の学びや巣立つ 庄内地方多くの中学校卒業式
庄内地方の多くの中学校で14日、卒業式が行われ、卒業生たちがそれぞれの思いを胸に、3年間通い慣れた学びやを巣立った。
このうち、昨年7月の豪雨災害で氾濫した荒瀬川流域に位置する酒田市の鳥海八幡中学校(田中大校長、生徒186人)では、体育館で午前9時半から式が行われ、在校生と教職員、保護者ら計約350人が出席した。
卒業生64人が拍手の中入場。田中校長が一人一人に卒業証書を手渡した後、「可能性に向き合う過程や試行錯誤が人生を豊かにしてくれる。不完全であることを恐れず、未来の景色に出会う喜びを胸に、積極的に向き合ってほしい」と式辞を述べた。祝辞、送辞に続き、卒業生代表の島田瑠々伽さん(15)が「仲間と共に学び、笑った3年間はかけがえのない宝物。卒業生64人の中の一員であった誇りを胸に、これからの人生を精いっぱい歩み続けます」と「旅立ちの言葉」を述べた。
在校生たちから合唱のはなむけが贈られた後、卒業生たちが登壇し「3月9日」「群青」を合唱披露。3年間の中学生活を振り返り時折、涙を見せながらも背筋を伸ばし、美しいハーモニーを響かせた。立派に成長した生徒やわが子の姿を、教職員や保護者らは目頭を押さえながら見つめていた。
2025年(令和7年) 3月15日(土)付紙面より
ツイート全国認知症キッズサポーター研究作品展 坂東さん(斎小5年)特別賞受賞 認知症マフ掘り下げ効果実践
認知症についての自由研究を3年間続けている鶴岡市の斎小5年、坂東志麻さん(11)が、「認知症への理解」をテーマに全国の認知症キッズサポーターを対象にした作品募集の自由作品小学生部門で特別賞を受賞した。昨年の最優秀賞に続き、2年連続の受賞。
受賞のテーマは「認知症への思い~認知症マフを通して感じたこと~」。認知症マフはニット製の筒状のもので、両側から手を入れ、中に取り付けたマスコットなどを触ることで安心感が得られるとして、介護の現場などで活用されている。坂東さんは曽祖母が使っていたことで興味を持ち、小学3年から研究を続けており、昨年は認知症マフの効果などを現場で聞き取りしたものをまとめたところ、「社会に役立つ大変優れた報告」として表彰された。
5年生では、認知症マフを使っている人の「マフは毛糸なので、夏用のものが欲しい」という声を聞き、ミシン店が行う手芸教室に通ってアドバイスをもらい、外側をタオル地、内側をガーゼで縫い合わせて作った。すると「夏も涼しい。洗濯機でも洗えるので便利」と喜びの手紙をもらったという。
表彰式は今年1月に東京都で行われた。日頃から鶴岡市などが主催する認知症を理解する講座などで知識を深めている坂東さん。受賞について「2年続けて賞がもらえるとは思わなかった。マフを使うことで気持ちが穏やかになり、介護する人も安心できる。いろんな人が認知症について正しく理解してくれたらうれしい」と話し、6年生の自由研究では「若年性認知症について研究したい」と、今から準備しているという。
- フリーペーパー

気になるお口の健康について、歯科医の先生方が分かりやすく解説します- 特集企画

酒井家庄内入部400年を記念し、徳川家康の重臣として活躍した酒井家初代・忠次公の逸話を交え事績をたどる。
酒井家庄内入部400年を記念し、庄内藩中興の祖と称された酒井家9代・忠徳公の業績と生涯をたどる。
江戸幕府が3大名に命じた転封令。幕命撤回に至る、庄内全域で巻き起こった阻止運動をたどる。
酒井家3代で初代藩主として、庄内と酒井家400年の基盤を整えた忠勝公の事績をたどる。
幕末~明治・大正の激動期の庄内藩と明治維新後も鶴岡に住み続けた酒井家の事績をたどる。
酒井家が藩主として庄内に入部し400年を迎えます。東北公益文科大学の門松秀樹さんがその歴史を紹介します。
教育現場に身を置く筆者による提言の続編です。
子どもたちを取り巻く環境は日々変化しています。長らく教育現場に身を置く筆者が教育をテーマに提言しています。
鶴岡市櫛引地域出身の大相撲の元横綱・柏戸の土俵人生に迫ります。本人の歩み、努力を温かく見守った家族・親族や関係者の視点も多く交えて振り返ります。
藤沢周平作品の魅力を研究者などの視点から紹介しています
世界あるいは全国で活躍し、各分野で礎を築いた庄内出身の先人・先覚たちを紹介しています
旬の食べ物を使った、おいしくて簡単、栄養満点の食事のポイントを学んでいきましょう
庄内の「うまいもの」を関係者のお話などを交えながら解説しています